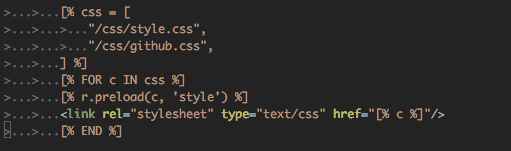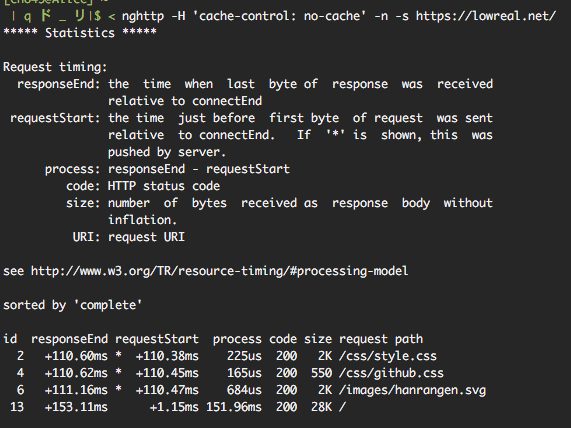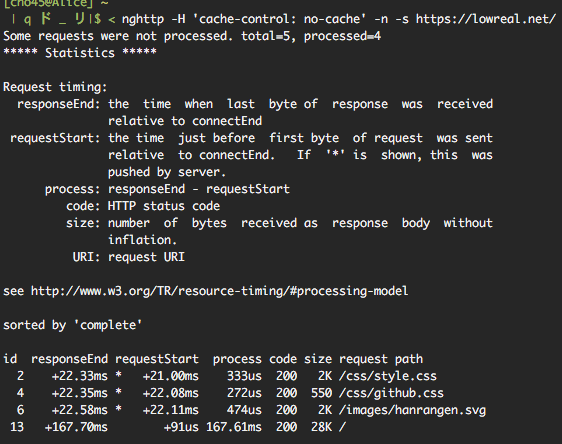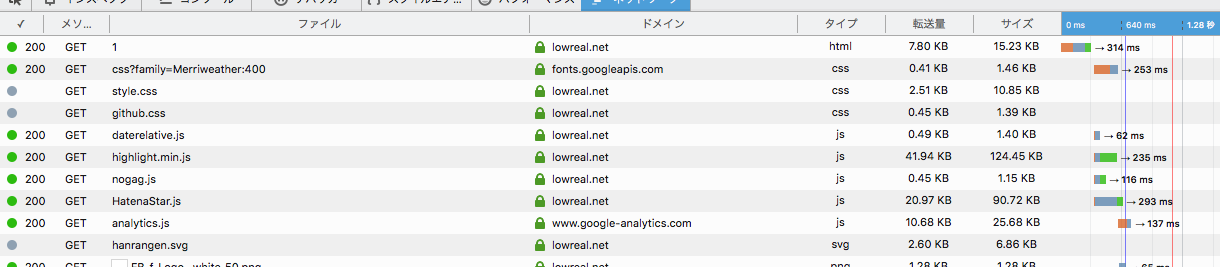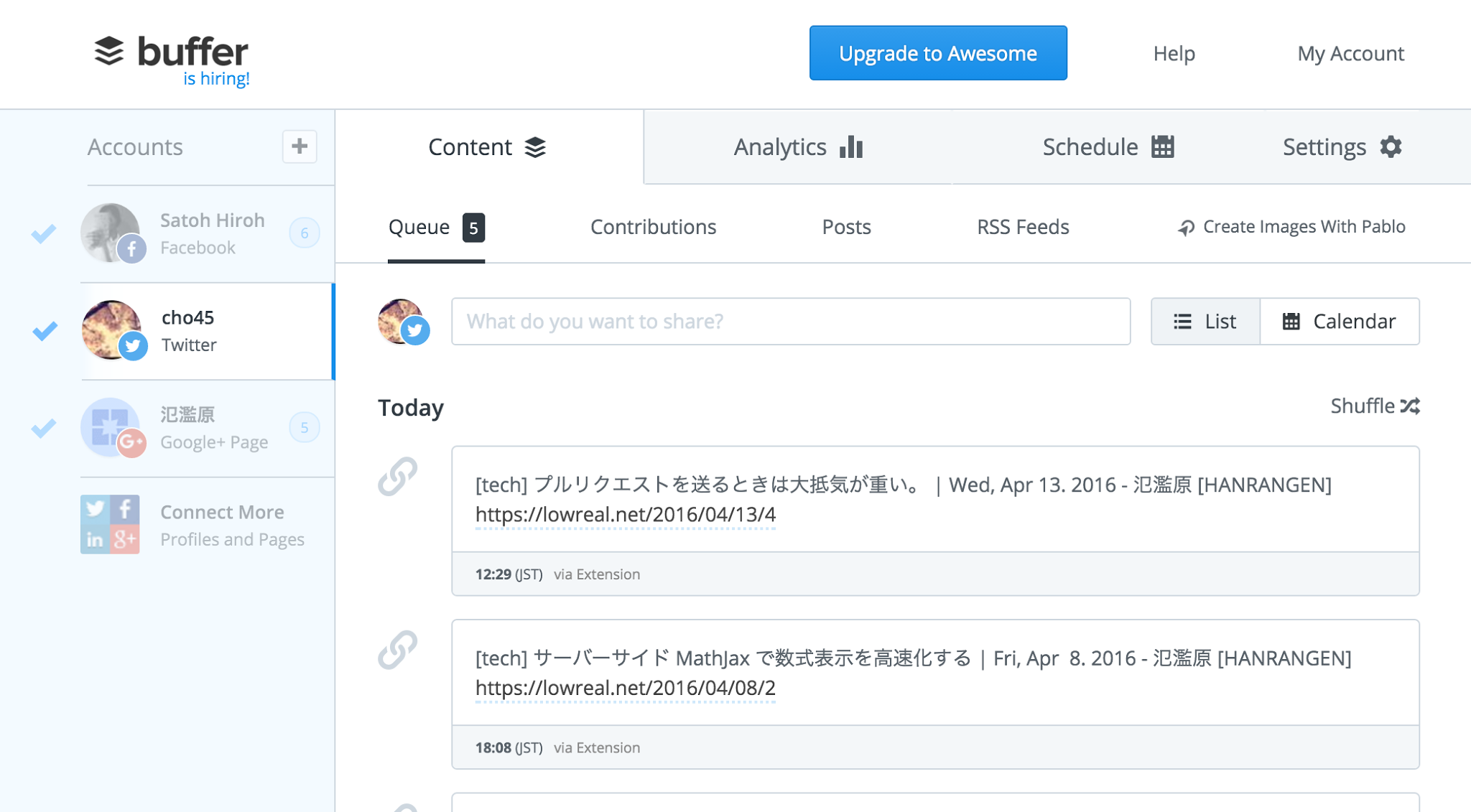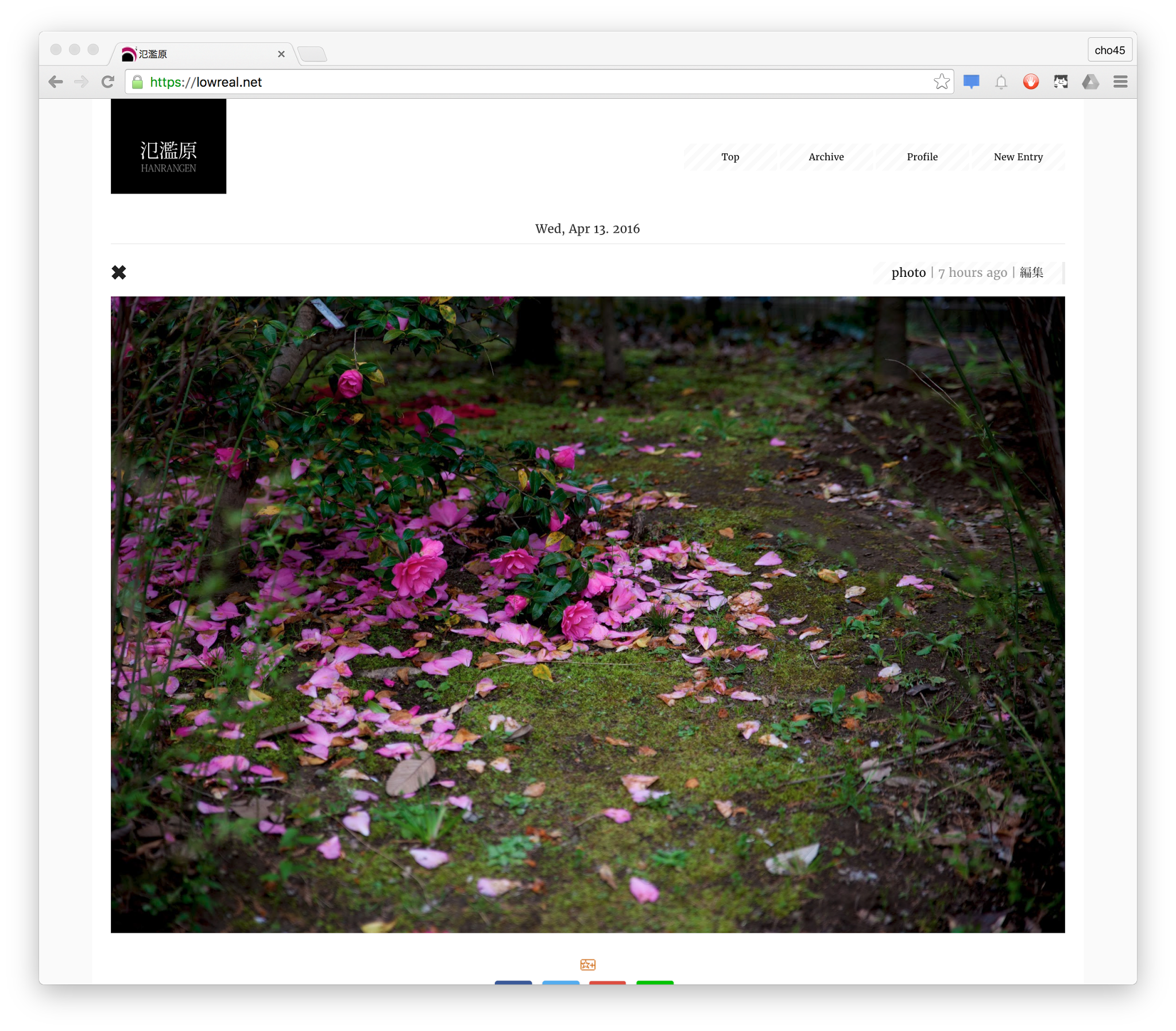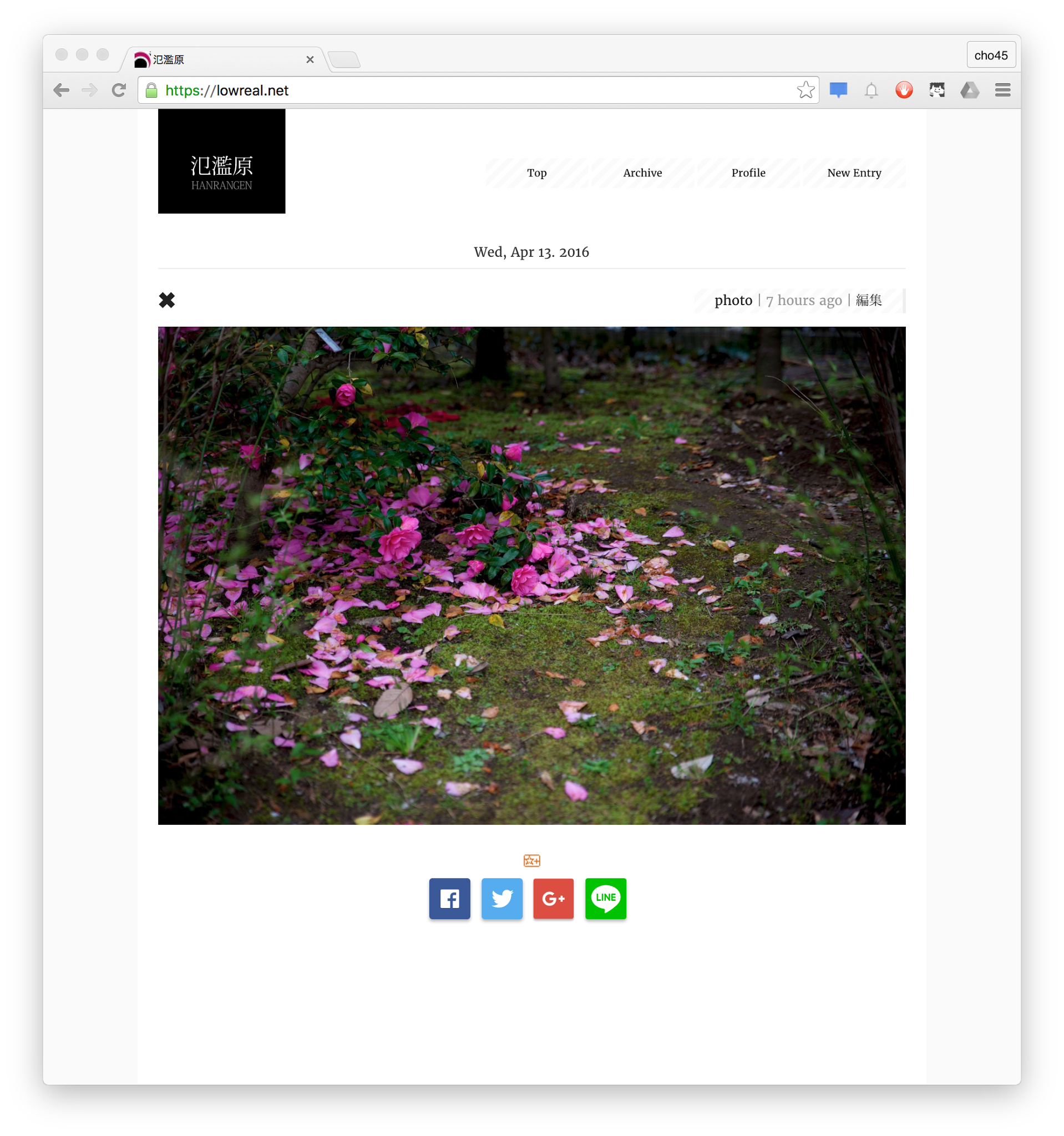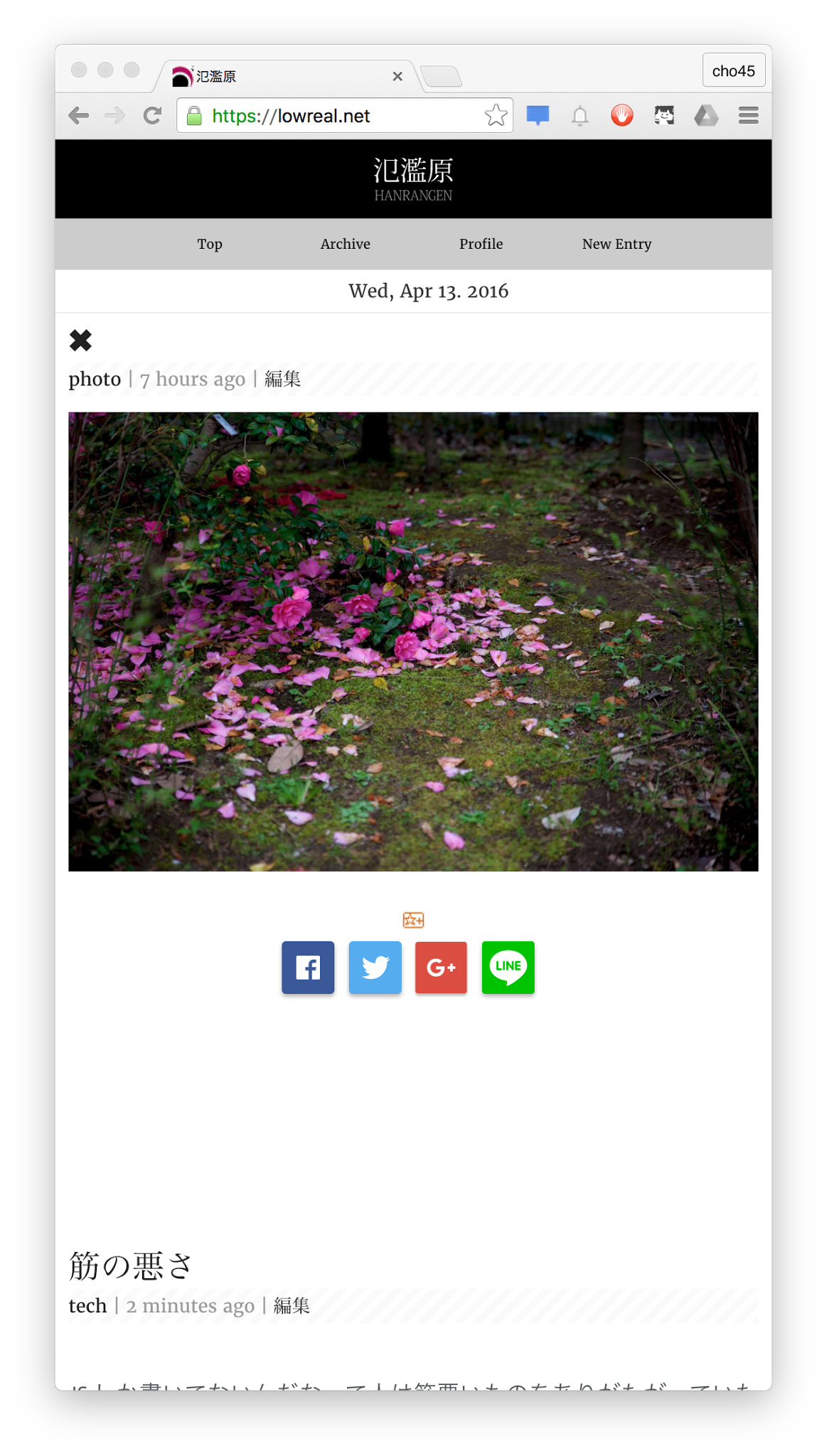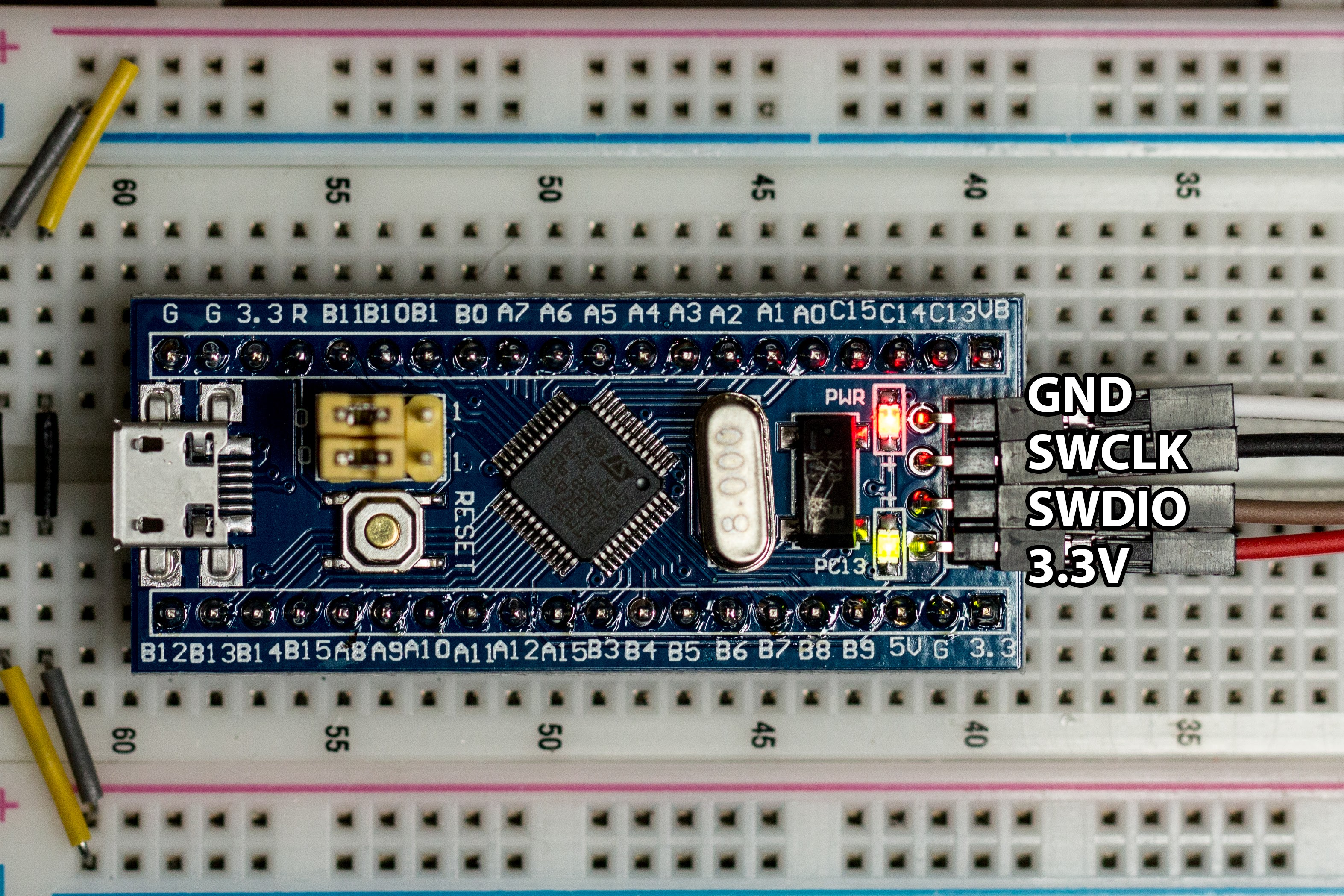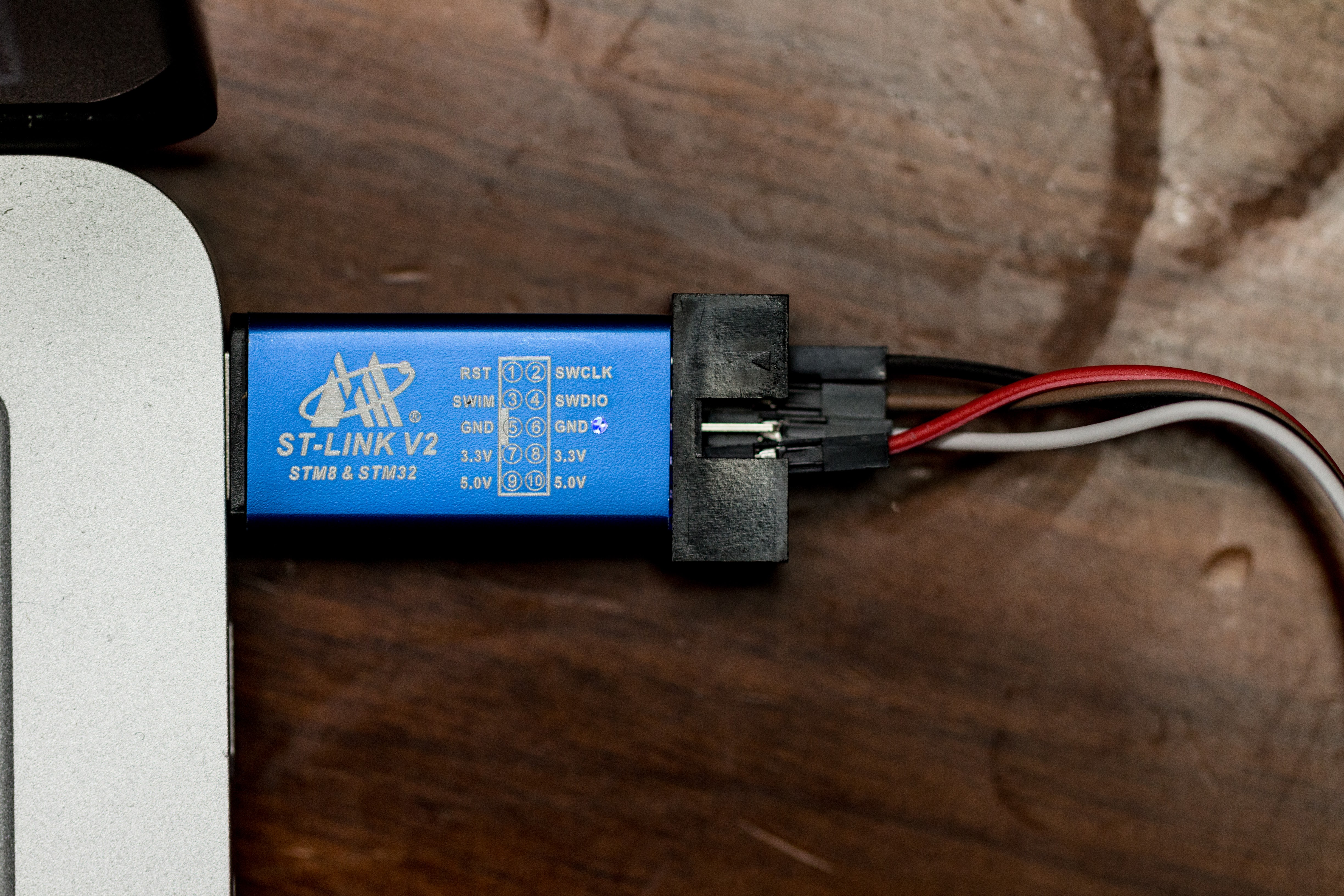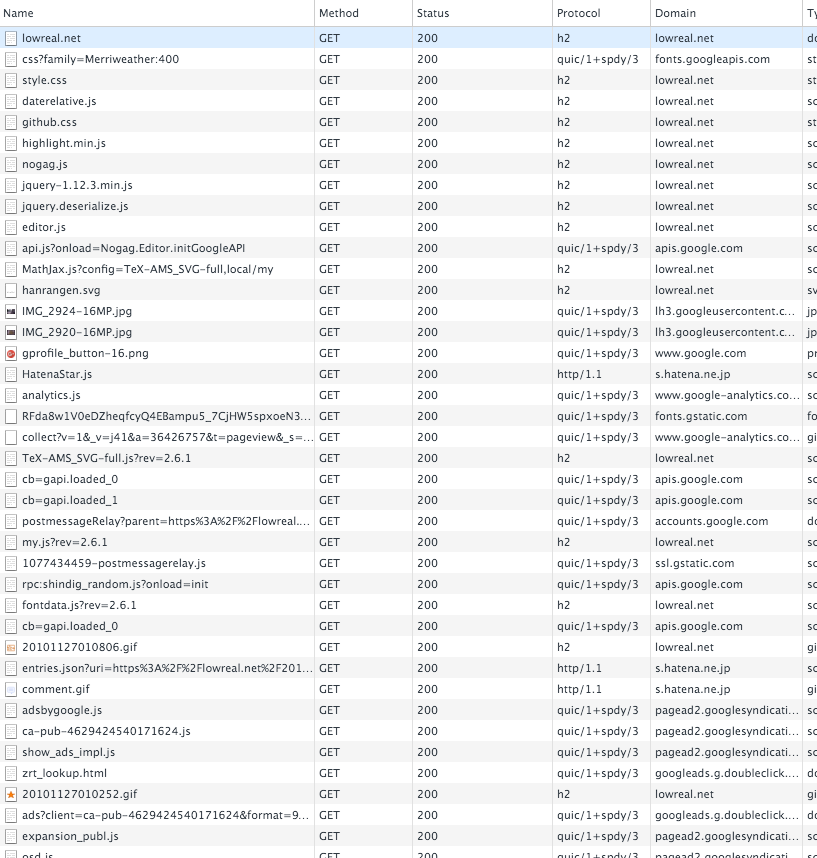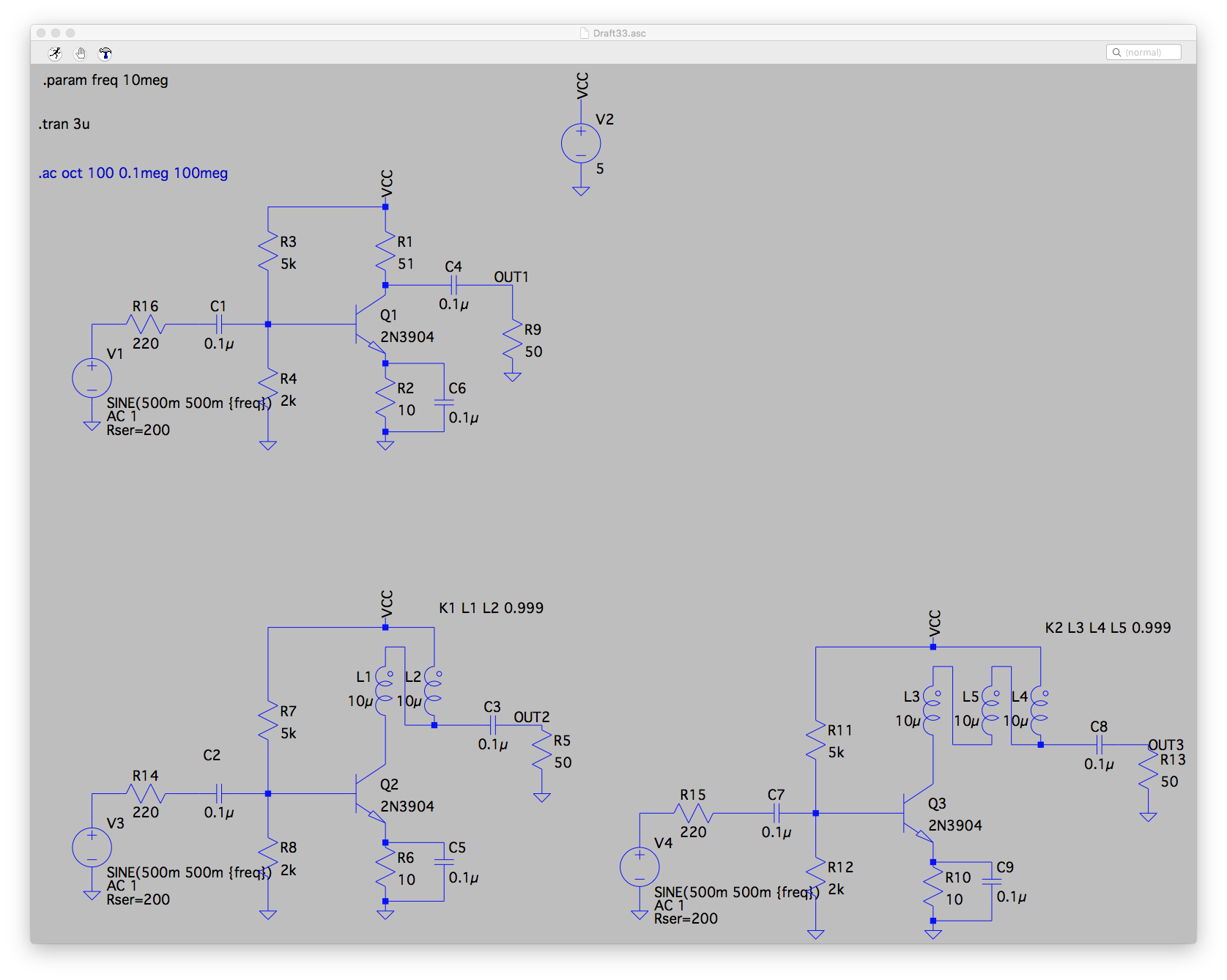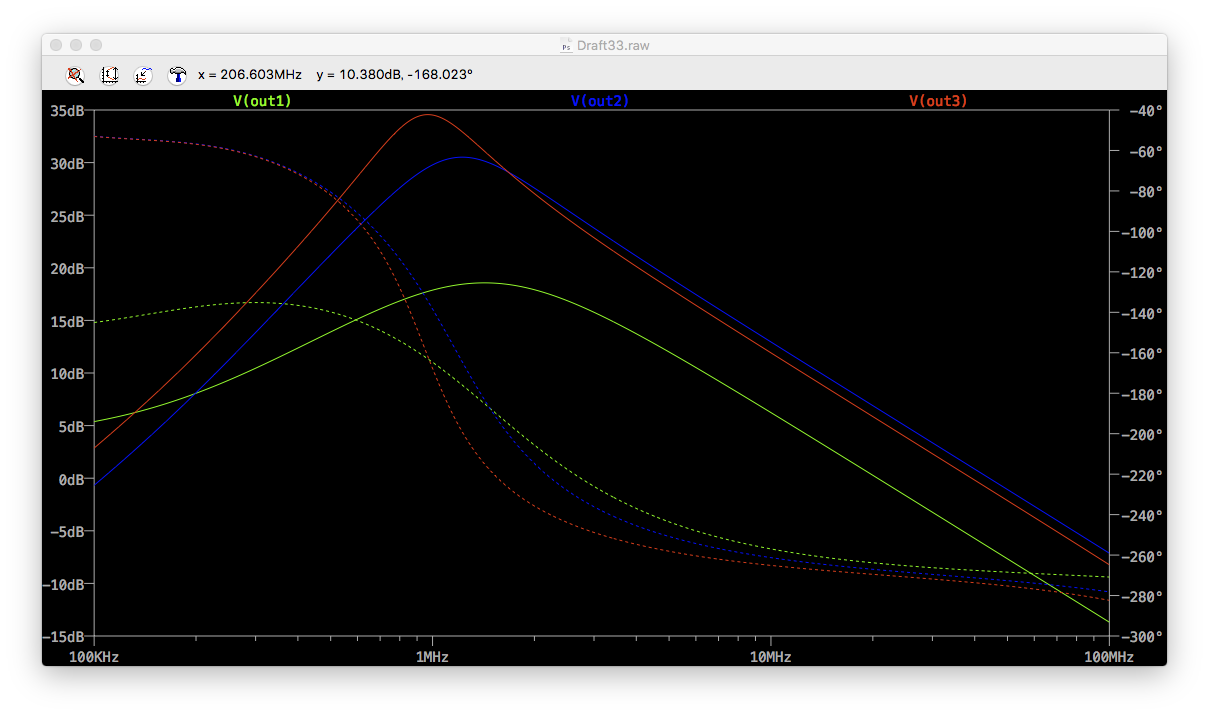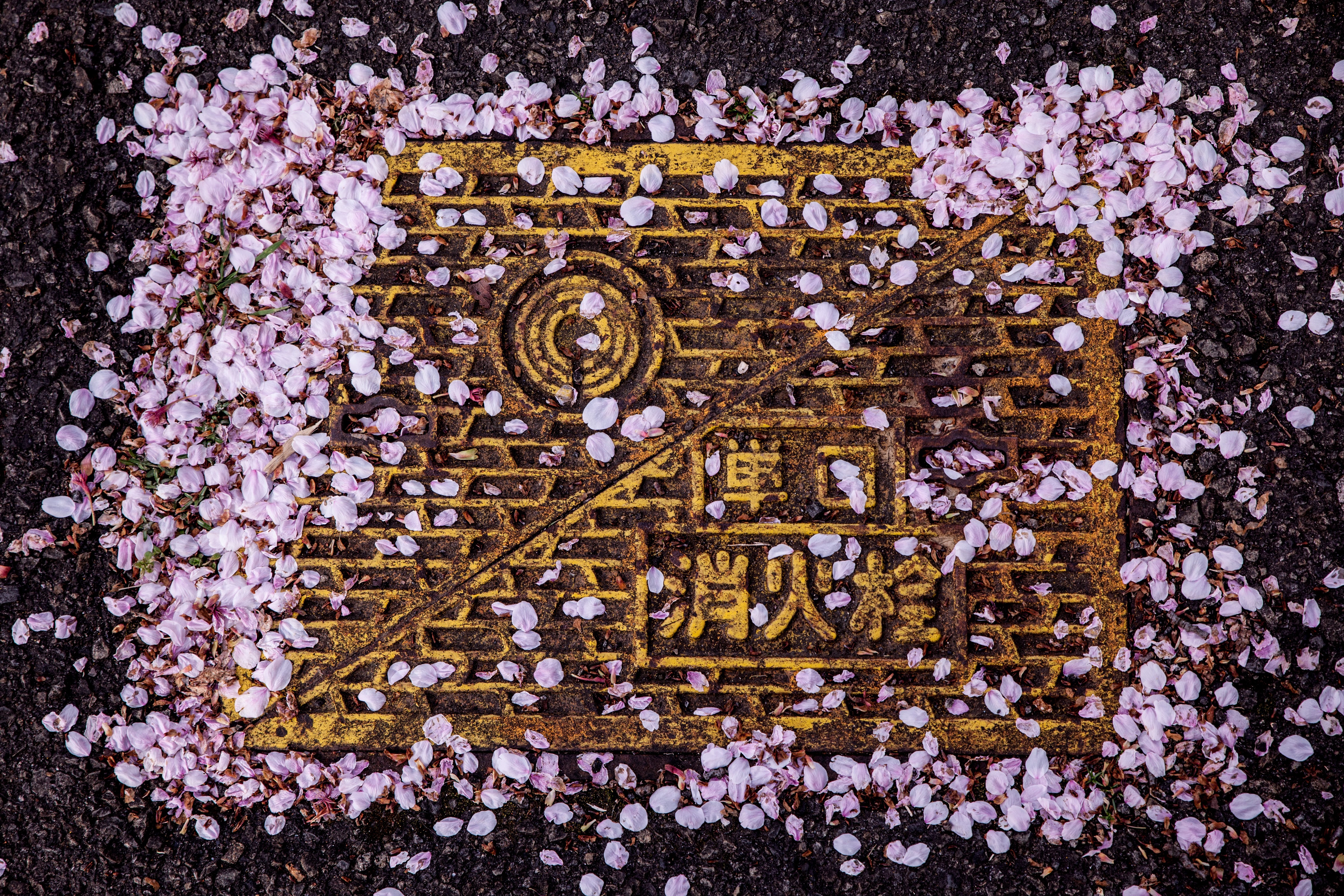今のこのサイトの h2o.conf.yaml です。HTTPS (443) のみを処理しています。HTTP (80) は nginx で受けていて、HTTPS 対応ホストに関しては nginx からはリダイレクトしています。
- アクセスログフォーマットを LTSV に
- ログフォーマットを YAML の参照で全ホストで共有
- rewrite rule
- Strict-Transport-Security (HSTS)
- 一旦 https でアクセスしてきたクライアントに対して以後 http でのアクセスをさせない
- 本来はセキュリティのためだが、リダイレクトを一回減らせるのでパフォーマンス的にも一応得
- "/.well-known": をバインド
設定の際参考になれば幸いです。
user: www-data
access-log: &ACCESSLOG
path: /var/log/h2o/access.log
format: "time:%t\thost:%h\treq:%r\tstatus:%s\tsize:%b\treferer:%{Referer}i\tua:%{User-Agent}i\tcache:%{X-Cache}o\truntime:%{X-Runtime}o\tvhost:%{Host}i\tconnect-time:%{connect-time}x\trequest-header-time:%{request-header-time}x\trequest-body-time:%{request-body-time}x\tprocess-time:%{process-time}x\tresponse-time:%{response-time}x\tduration:%{duration}x\thttp2.stream-id:%{http2.stream-id}x\thttp2.priority:%{http2.priority.received}x"
error-log: /dev/stdout
http2-reprioritize-blocking-assets: ON
ssl-session-resumption:
mode: all
hosts:
"lowreal.net:443":
access-log:
<<: *ACCESSLOG
path: /var/log/h2o/lowreal.net.access.log
http2-casper: ON
compress: ON
listen:
port: 443
ssl:
certificate-file: /etc/letsencrypt/live/lowreal.net/fullchain.pem
key-file: /etc/letsencrypt/live/lowreal.net/privkey.pem
header.add: "Strict-Transport-Security: max-age=31536000"
header.add: "X-Content-Type-Options: nosniff"
header.add: "X-UA-Compatible: IE=Edge"
paths:
"/":
reproxy: ON
mruby.handler: |
require "/srv/www/rewrite_rules.rb"
lambda do |env|
RewriteRules.rewrite(env) do
rewrite '/favicon.ico', '/images/favicon.ico', :break
rewrite '/apple-touch-icon.png', '/images/apple-touch-icon.png', :break
rewrite %r{^/2005/colors-canvas\.xhtml$}, '/2005/colors-canvas.html', :permanent
rewrite %r{^/2005/colors-canvas$}, '/2005/colors-canvas.html', :permanent
rewrite %r{^/logs/latest$}, '/', :permanent
rewrite %r{^/logs/latest.rdf$}, '/feed', :permanent
rewrite %r{^/logs/latest.atom$}, '/feed', :permanent
rewrite %r{^/latest\.rdf$}, '/feed', :permanent
rewrite %r{^/blog/index\.(rdf|atom)$}, '/feed', :permanent
rewrite %r{^/logs(/.+?)(\.(rdf|atom))$}, '/feed', :permanent
rewrite %r{^/logs(/.+?)(\.(x?html|xml|txt))?$}, '\1', :permanent
rewrite %r{^/blog(/.+?)(\.(x?html|xml|txt))?$}, '\1', :permanent
rewrite %r{^/photo$}, '/photo/', :permanent
rewrite %r{^/(\d\d\d\d/\d\d(/\d\d)?)$}, '/\1/', :permanent
rewrite %r{^/\d\d\d\d/$}, '/', :redirect
rewrite %r{^/view-img(/.+?)$}, '\1', :permanent
rewrite %r{^/(\d\d\d\d/([^\d]|\d\d[^/]).*)}, '/files/\1', :break
end
end
proxy.reverse.url: http://localhost:5001
proxy.preserve-host: ON
"/files":
file.dir: /srv/www/lowreal.net/files
"/images":
file.dir: /srv/www/lowreal.net/Nogag/static/images
"/css":
file.dir: /srv/www/lowreal.net/Nogag/static/css
"/js":
file.dir: /srv/www/lowreal.net/Nogag/static/js
"/lib":
file.dir: /srv/www/lowreal.net/Nogag/static/lib
"/.well-known":
file.dir: /srv/www/lowreal.net/.well-known
"www.lowreal.net:443":
access-log:
<<: *ACCESSLOG
path: /var/log/h2o/www.lowreal.net.access.log
http2-casper: ON
compress: ON
listen:
port: 443
ssl:
certificate-file: /etc/letsencrypt/live/www.lowreal.net/fullchain.pem
key-file: /etc/letsencrypt/live/www.lowreal.net/privkey.pem
header.add: "Strict-Transport-Security: max-age=31536000"
header.add: "X-Content-Type-Options: nosniff"
header.add: "X-UA-Compatible: IE=Edge"
paths:
"/":
reproxy: ON
mruby.handler: |
lambda do |env|
link = [
'/styles/201002/201002.css',
'/js/site-script.js',
].map{|p| "<#{p}>; rel=preload"}.join("\n")
case env['PATH_INFO']
when "/"
if (env['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'] || '') =~ /ja/
return [307, {"x-reproxy-url" => "/index.ja.html", "link" => link }, []]
else
return [307, {"x-reproxy-url" => "/index.en.html", "link" => link }, []]
end
when "/index.ja.html", "/index.en.html"
return [399, {"link" => link }, []]
end
return [399, {}, []]
end
file.dir: /srv/www/www.lowreal.net
# file.index: [ index.en.html ]
"cho45.stfuawsc.com:443":
access-log:
<<: *ACCESSLOG
path: /var/log/h2o/cho45.stfuawsc.com.access.log
listen:
port: 443
ssl:
certificate-file: /etc/letsencrypt/live/cho45.stfuawsc.com/fullchain.pem
key-file: /etc/letsencrypt/live/cho45.stfuawsc.com/privkey.pem
header.add: "Strict-Transport-Security: max-age=31536000"
header.add: "X-Content-Type-Options: nosniff"
header.add: "X-UA-Compatible: IE=Edge"
paths:
"/":
file.dir: /srv/www/cho45.stfuawsc.com
redirect:
status: 301
url: "/niro/"
"/niro/":
proxy.reverse.url: http://localhost:5001/niro/
proxy.preserve-host: ON
"/tmp":
mruby.handler: |
require "htpasswd.rb"
Htpasswd.new("/srv/www/.htpasswd", "Restricted")
file.dir: /srv/www/cho45.stfuawsc.com/tmp
-
トップ
-
tech
-
現在の h2o.conf.yaml