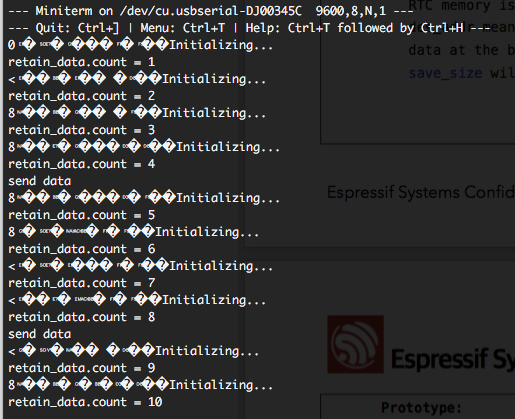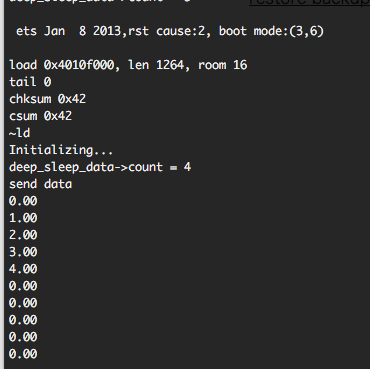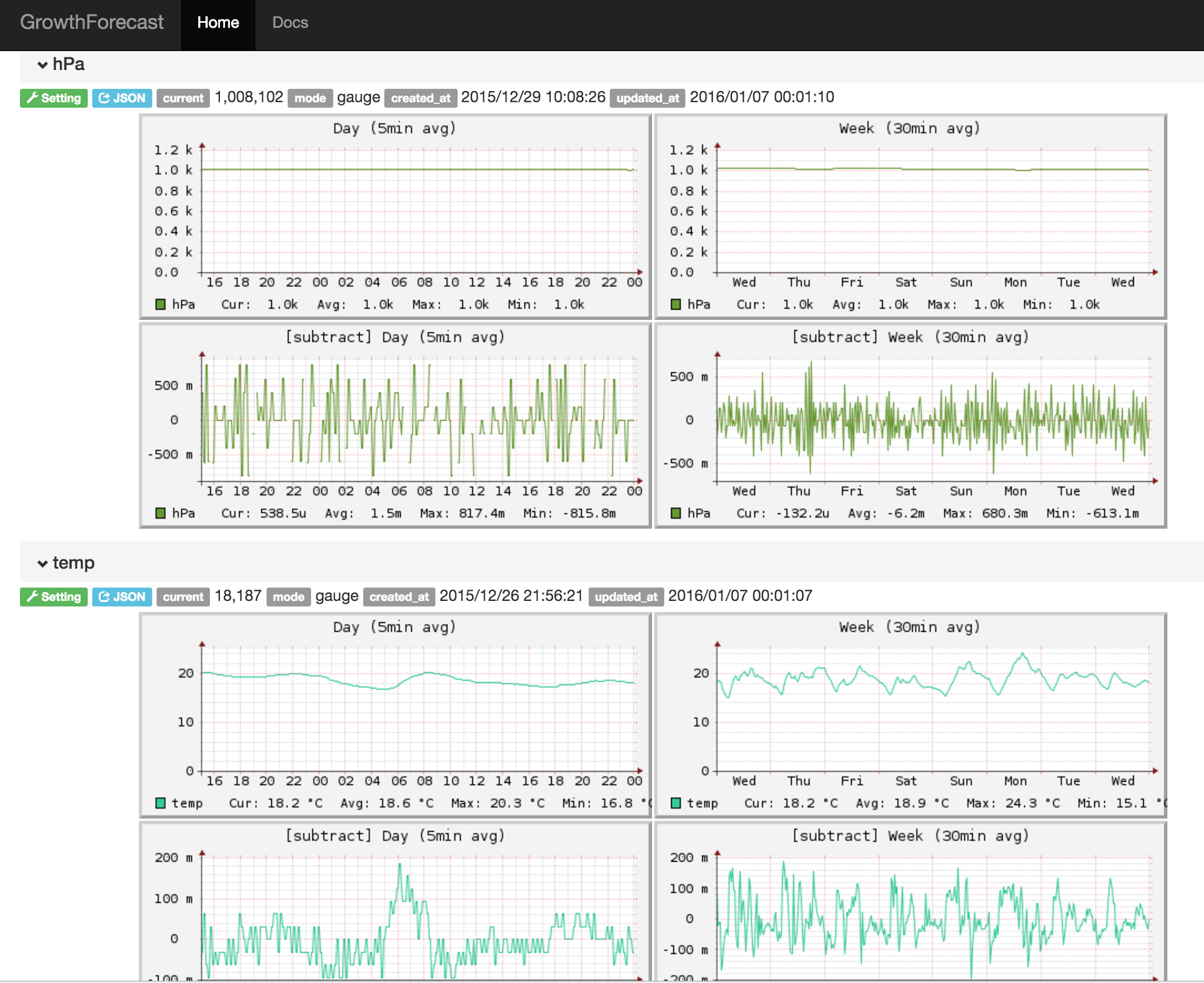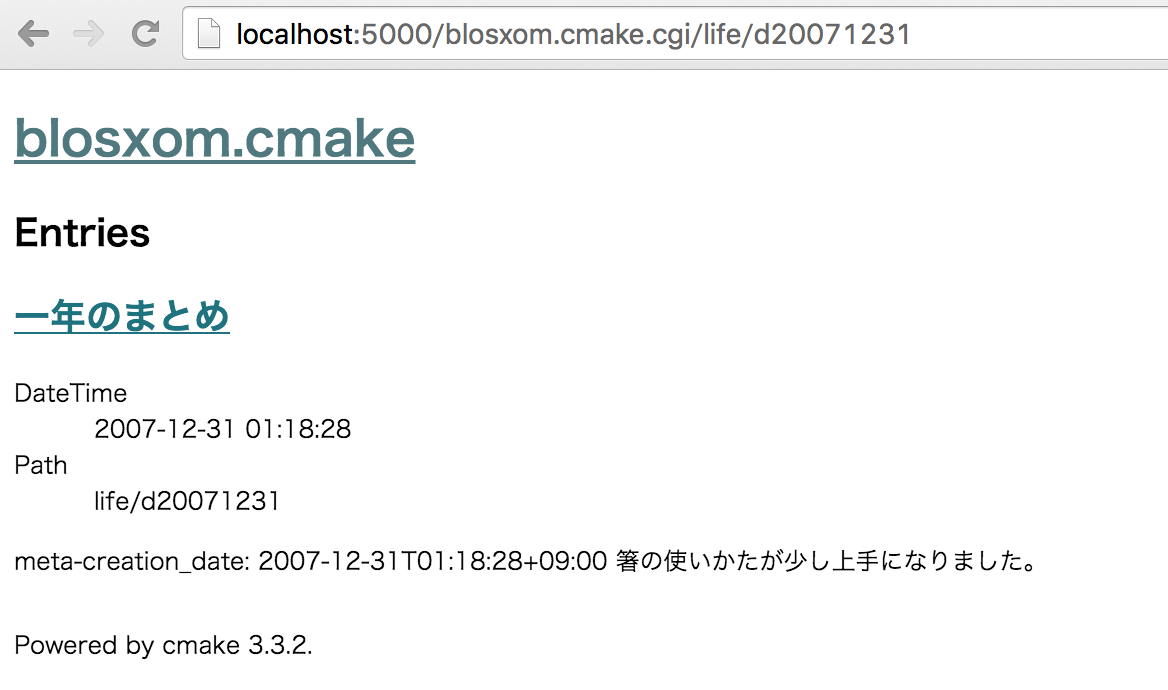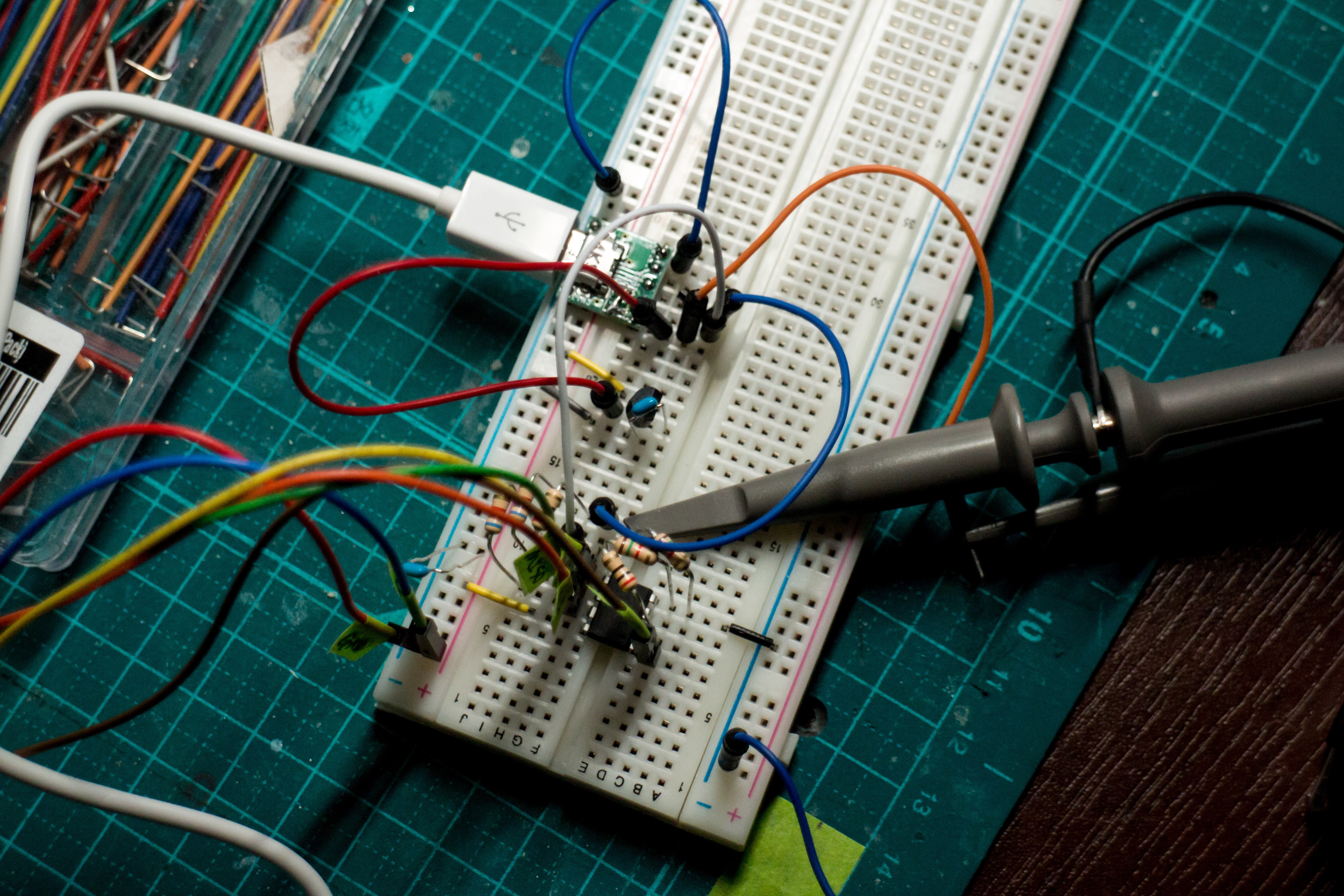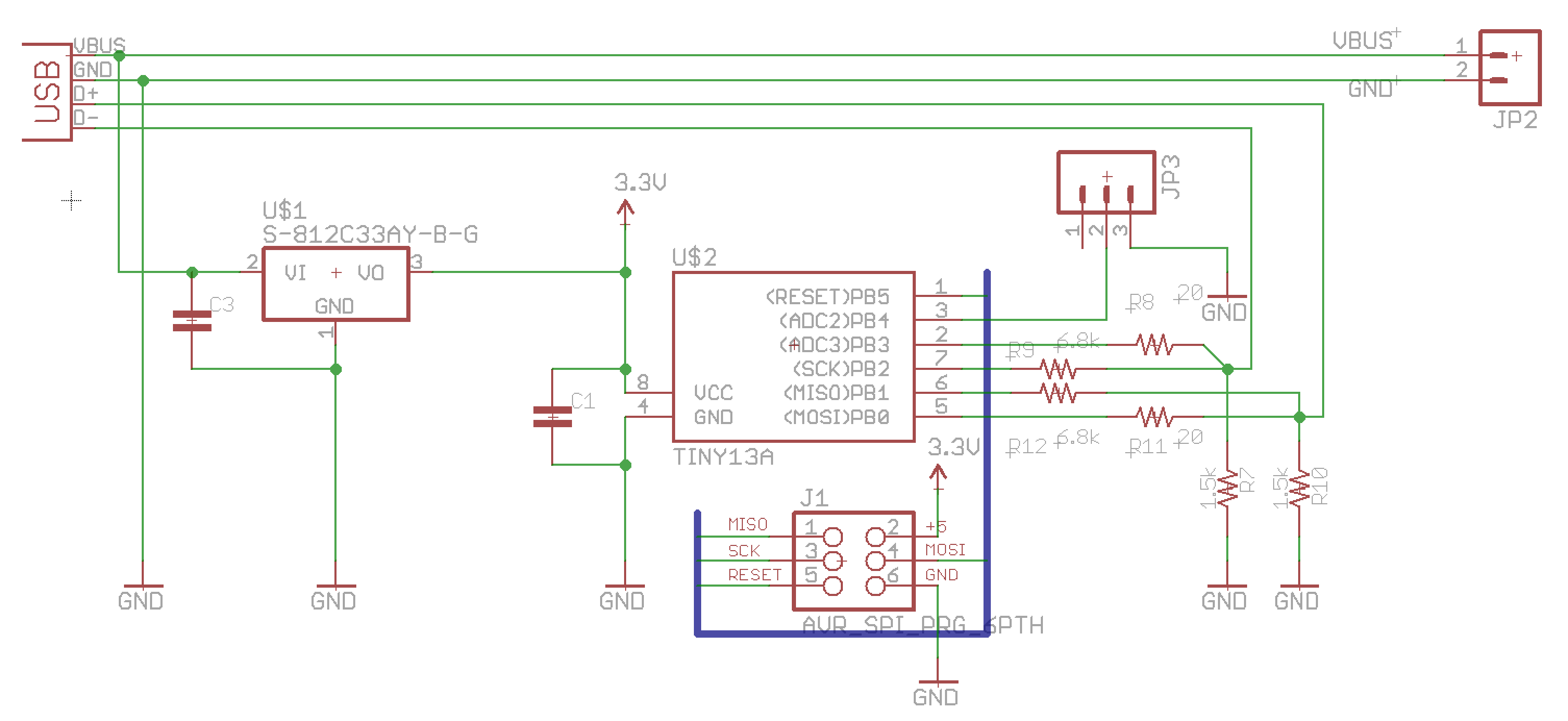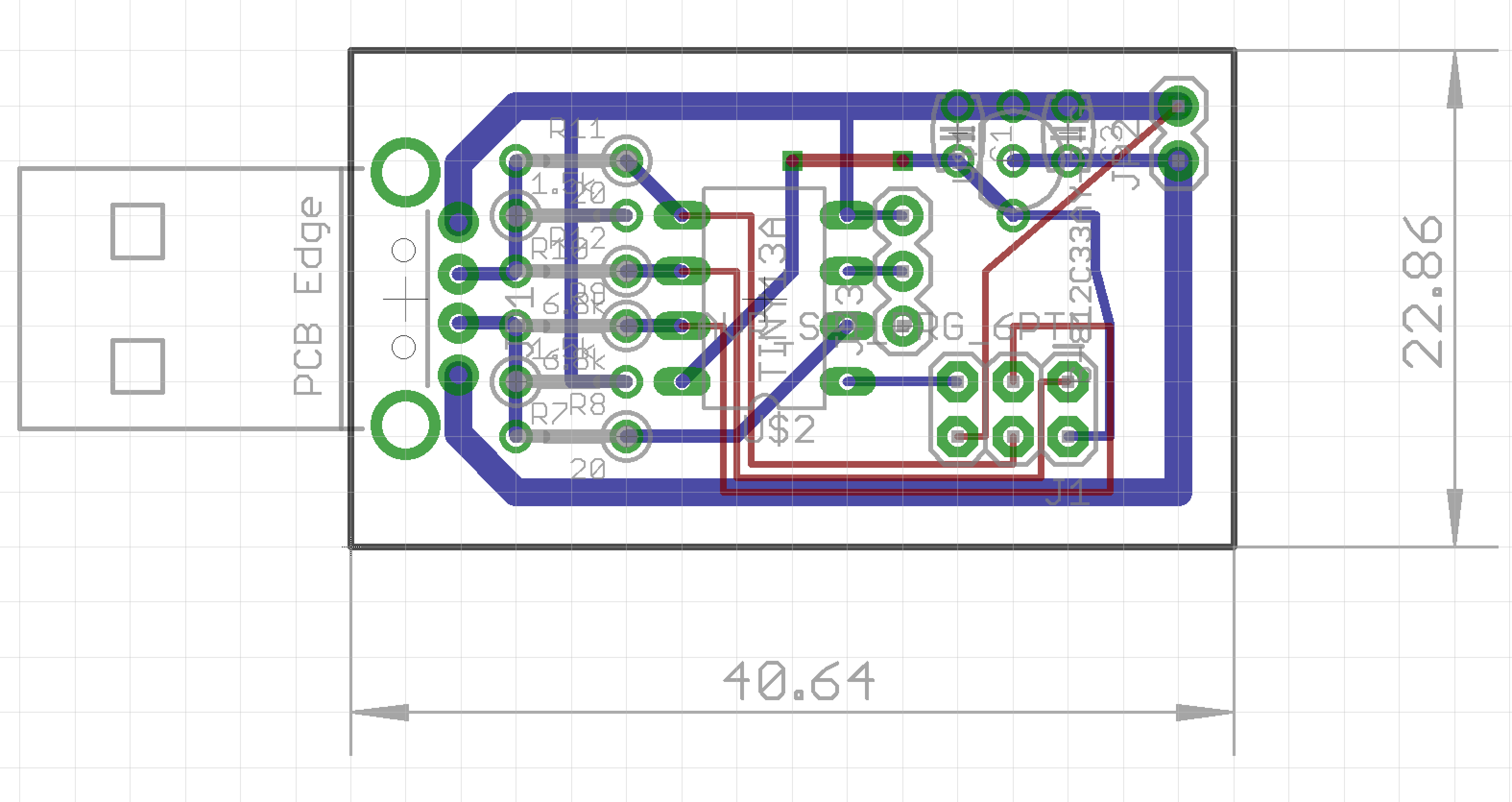I2Cセンサーとかを扱うと固定小数点表現によく出会う。が、固定小数点のままだと計算がめんどうなので、とりあえず浮動小数点に変換しときたいというケースがまぁまぁある。
そういうときに雑に使えるスニペットがほしかったので書いた。
#include <type_traits>
template <uint8_t int_bits, uint8_t fractional_bits, class T>
inline float fixed_point_to_float(const T fixed) {
static_assert(std::is_unsigned<T>::value, "argument must be unsigned");
constexpr uint8_t msb = int_bits + fractional_bits - 1;
constexpr T mask = static_cast<T>(~(( static_cast<T>(~0)) << msb));
constexpr float deno = 1<<fractional_bits;
if (fixed & (1<<msb)) {
return -( ( (~fixed & mask) + 1) / deno);
} else {
return fixed / deno;
}
} type_traits がない環境の場合、include と static_assert を消すだけで動く。これはエラーチェックにしか使ってなくて、もし消したとしても、負の signed を渡すと左シフトが不正になるのでエラーになる。
センサ出力とかの場合、8bit単位のビット数ではないことが多いので、渡された型のサイズに関わらずに処理できるようにマスクを作っている。
int main (int argc, char* argv[]) {
is(fixed_point_to_float<9, 4>((uint16_t)0b0000000000001), 0.0625);
is(fixed_point_to_float<9, 4>((uint16_t)0b0100101100000), 150.0);
is(fixed_point_to_float<9, 4>((uint16_t)0b0000000000000), 0);
is(fixed_point_to_float<9, 4>((uint16_t)0b1110010010000), -55.0);
is(fixed_point_to_float<9, 4>((uint16_t)0b1111111111111), -0.0625);
is(fixed_point_to_float<9, 4>((uint32_t)0b1111111111111), -0.0625 );
is(fixed_point_to_float<1, 11>((uint16_t)0x001) * (2.048), 1e-3);
is(fixed_point_to_float<1, 13>((uint16_t)0x001) * (2.048), 250e-6);
is(fixed_point_to_float<1, 15>((uint16_t)0x001) * (2.048), 62.5e-6);
is(fixed_point_to_float<13, 3>((uint16_t)0x3ECE), 2009.75);
is(fixed_point_to_float<3, 13>((uint16_t)0xB3F9), -2.37585);
is(fixed_point_to_float<2, 14>((uint16_t)0xC517), -0.92047);
is(fixed_point_to_float<1, 15>((uint16_t)0x33C8)/(1<<9), 0.000790);
volatile uint16_t x = 0x001;
is(fixed_point_to_float<1, 11>(x) * (2.048), 1e-3);
} テンプレートの第1引数は整数部(符号込み)のビット数・第2引数は小数点分のビット数
これはQ表記に対応する。
Q表記だと Q1.15 だと符号分1・整数部なし・15ビットの小数点桁。Q9.4 だと符号付き整数部8bit、小数部4bit。
メモ
固定小数点数用のクラス作って可能な限りは固定小数点で演算したほうがいい気はする。ヘッダ1ファイルとかで使えるの、当然もうありそうだけど見つけられてない。
-
トップ
-
tech
-
任意固定小数点→浮動小数点変換スニペット