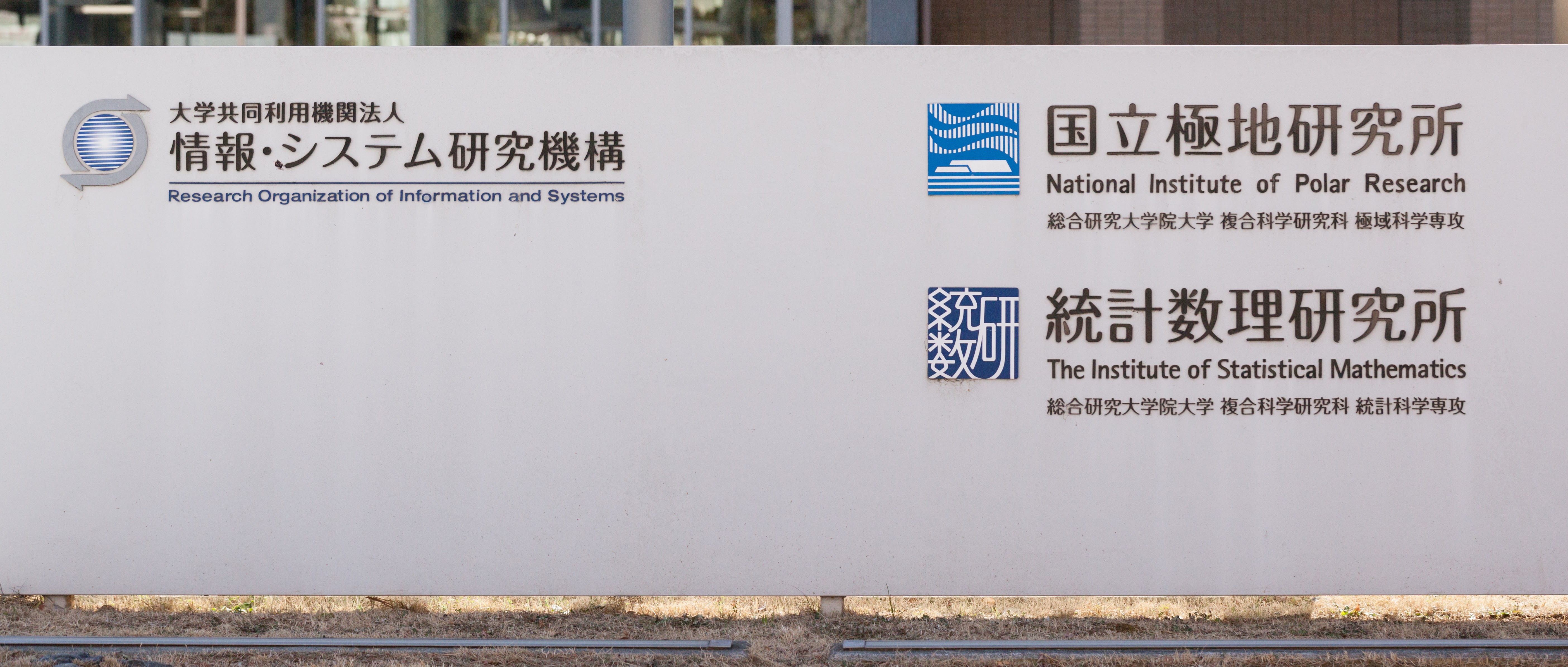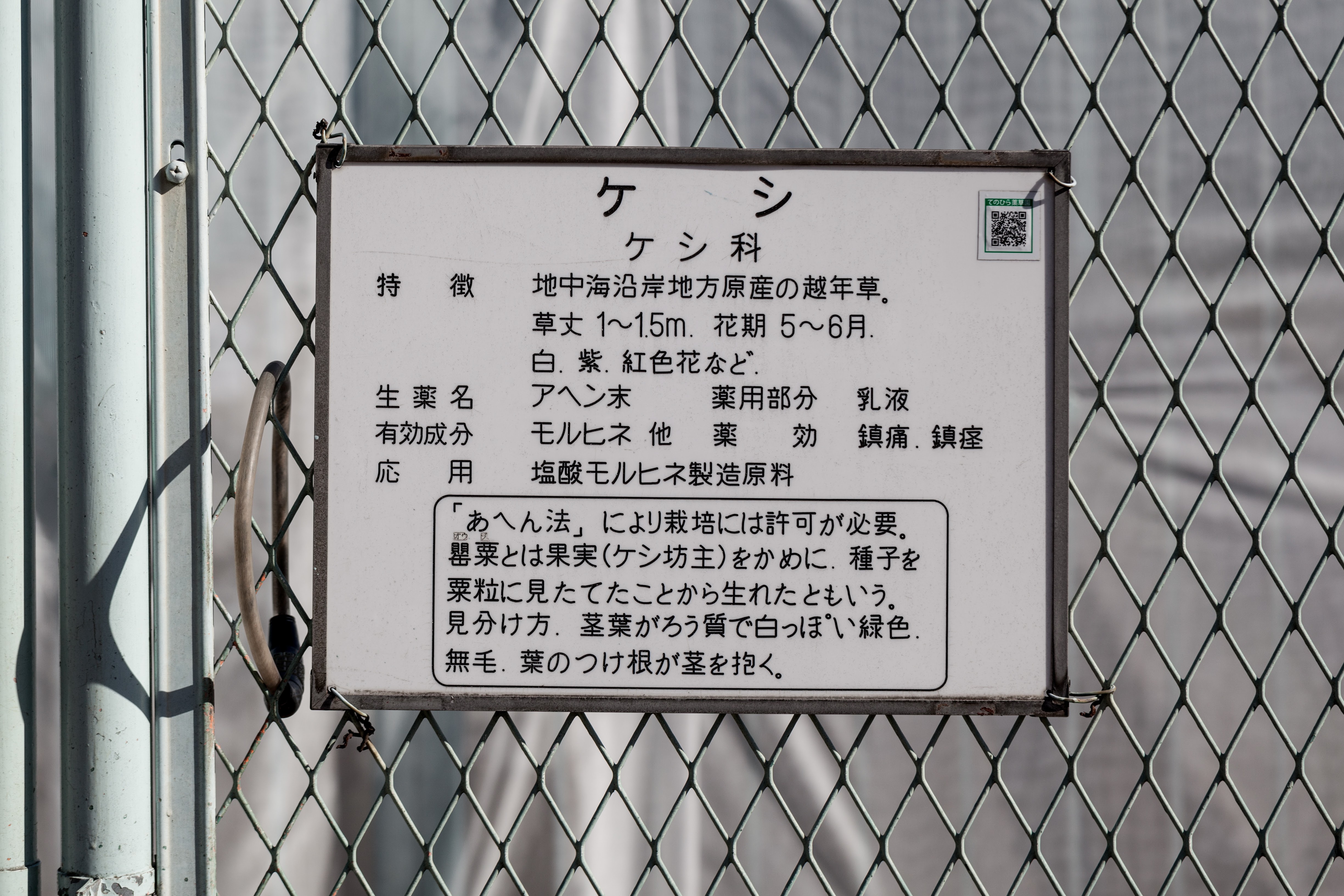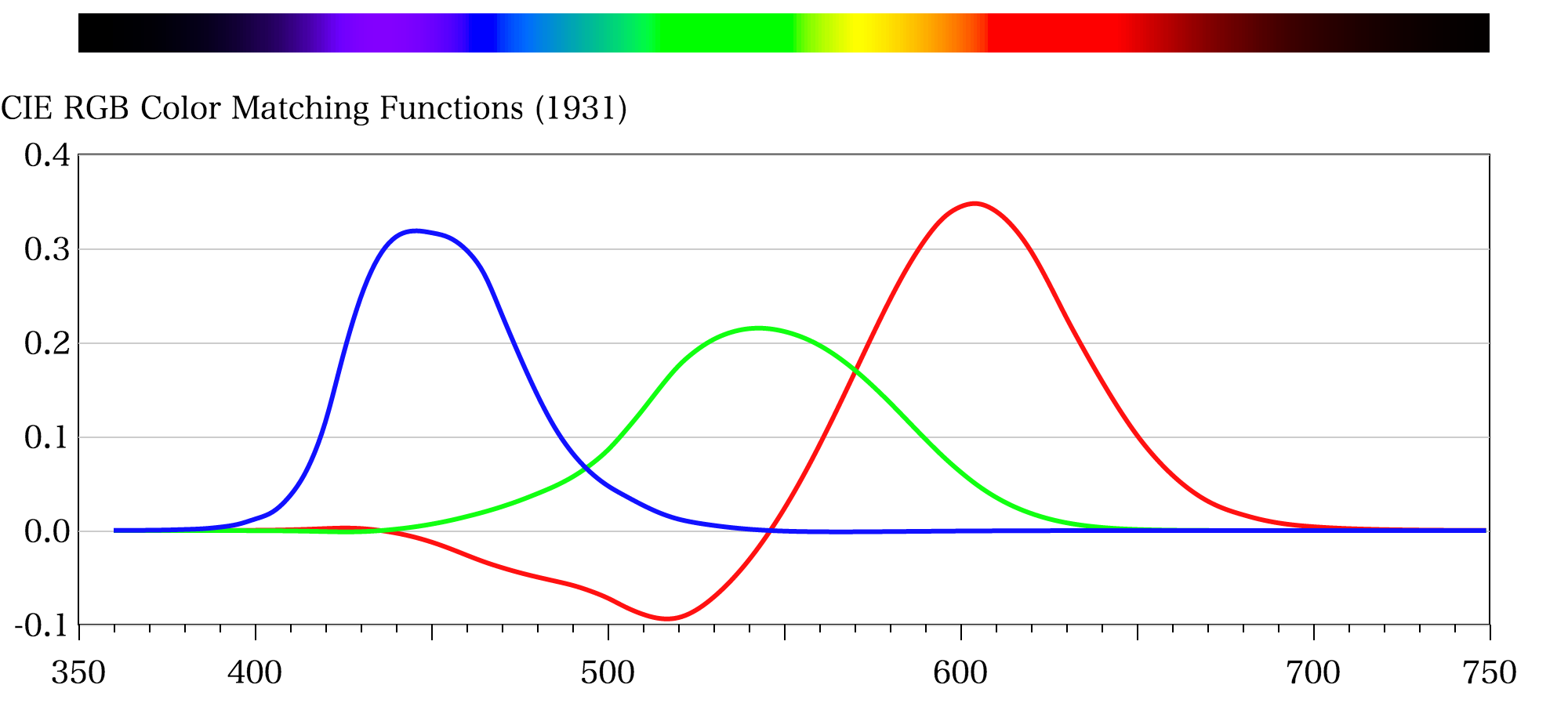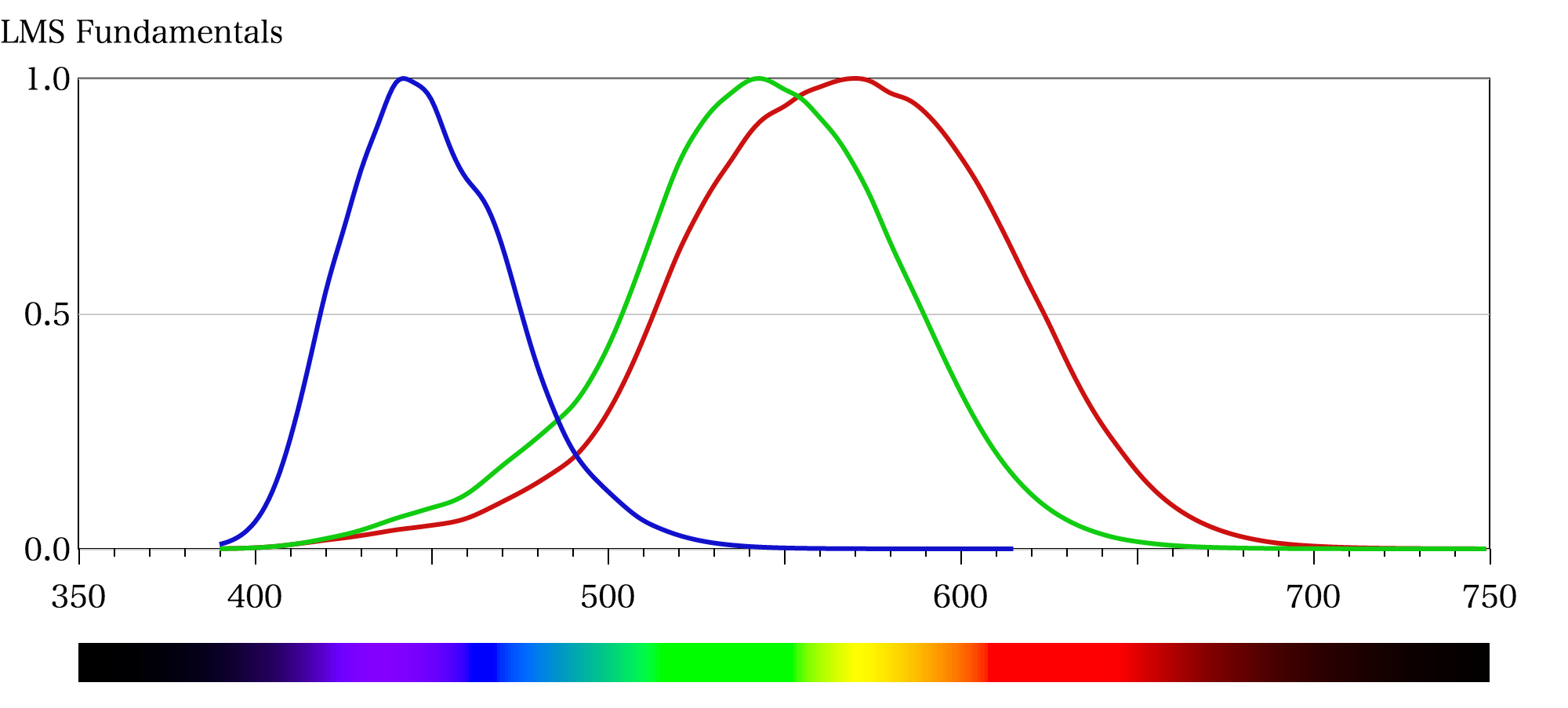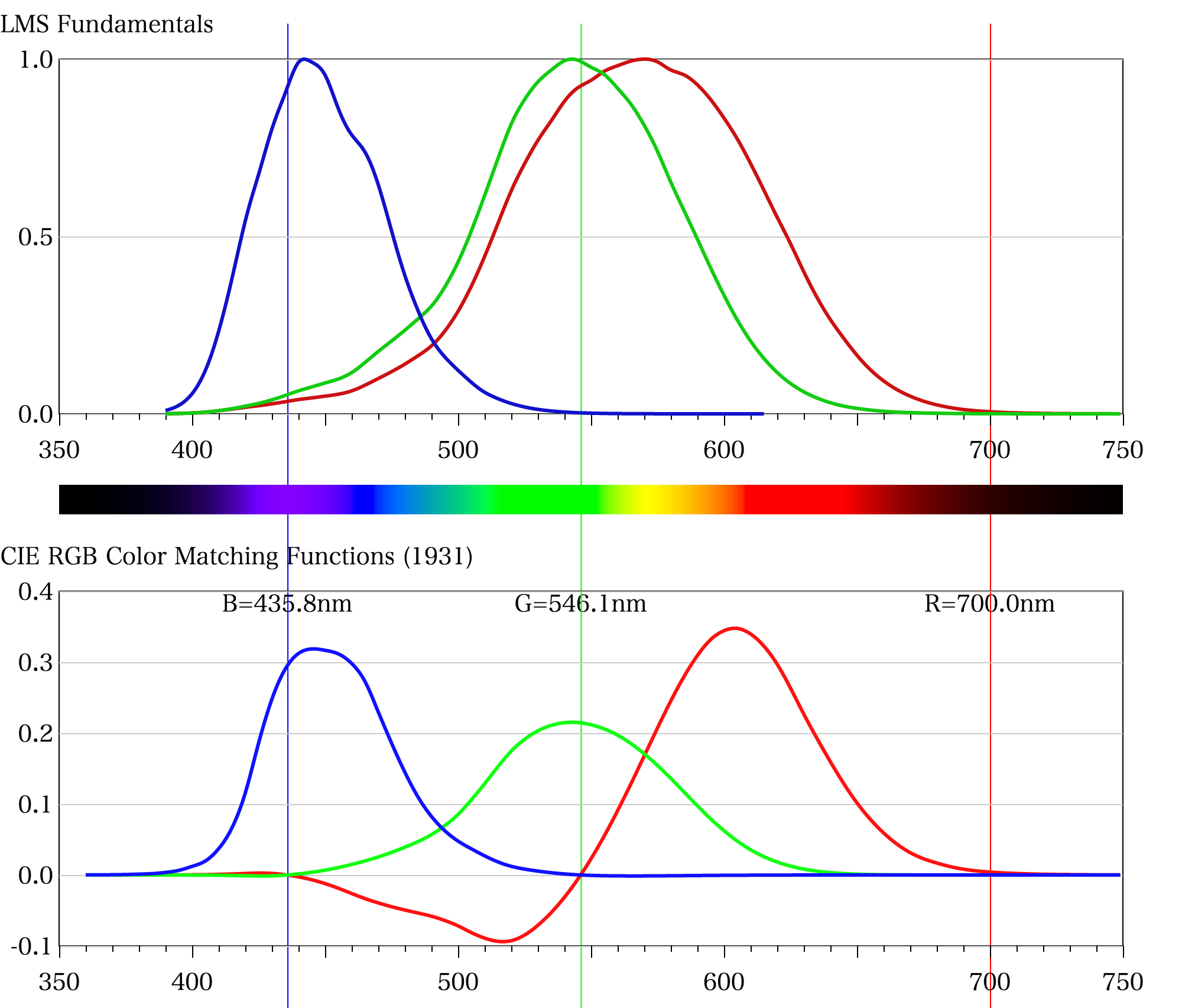なんで今まで使っていなかったのか…… と思いました。
前提として、Google Photos はアシスタントを有効にしていると、適当にアップロードするだけで自動的にアルバムを作ってくれます。旅行のときは位置情報も参照してアルバム名も適切に設定されたりします。これは勝手につくってくれて、作ったら勝手に通知がくるので、特に面倒なことは一切ありません。
この状態で、作られたアルバムを共有設定にするだけで、共有相手の Google Photos にも即座に共有され、表示できるようになります。ここまででやることはアルバムの共有設定だけ。
そして実は、共有された側からアルバムを開くと、Google Photos 内にアルバムに追加できそうな写真が自動的にサジェストされて、数タップで追加できます。そうすると共有アルバムで相互に写真共有されます。
旅行とかにいくとお互いにスマフォで撮った写真は端末に別々に保存されてしまうわけですが、Google Photos の共有だと、ほんとにわずかなステップで共有できて便利です。
通知も細かくて、共有設定をしたら相手に通知がいくのはもちろんのこととして、共有したアルバムを開いたときには「見たよ」という通知が返ってきます。
制限
1つのアルバムにつき2000枚までしか追加できないみたいです。通常あんまりひっかからないと思いますが、1つのアルバムに全部つっこんで共有ってのは難しいので、ちゃんと細かい単位でアルバムにしたほうが良いです。粒度的にはアシスタントがやるような感じで、1日1アルバムか、1旅行1アルバムとかになりそうです。
経緯
これまで Dropbox 経由で家族写真を妻と共有するようにしていましたが、容量制限が厳しいので限られた写真しか共有できていませんでした。基本的には Lightroom で厳選して現像したものだけを共有してて、大部分の写真は (共有していないという意味では) 実質的に捨てていたわけです。
一方、基本的に撮った写真は全て Google Photos にアップロードしていました。16MP までは無料ということで特に迷いなくただただアップロードしていただけです。
アルバム機能は知ってはいましたが基本的に無視をしていて、使っていませんでした。なぜ無視をしていたかというと、共有設定しても妻側でちゃんと見れるのかを確かめるのが面倒くさかったからというのがあります。
しかし今や Google Photos は独立サービスになっており、Android の写真バックアップの中心的なアプリケーションになっているわけなので、既に使われており、特に面倒なことはありませんでした。共有設定するだけで何も問題なく通知が飛んで見れる状態になっていました。