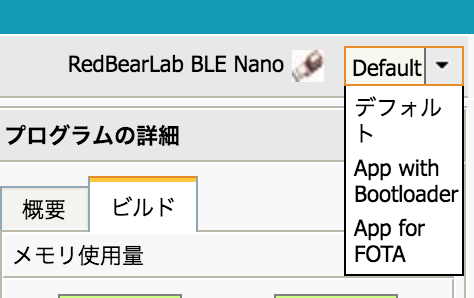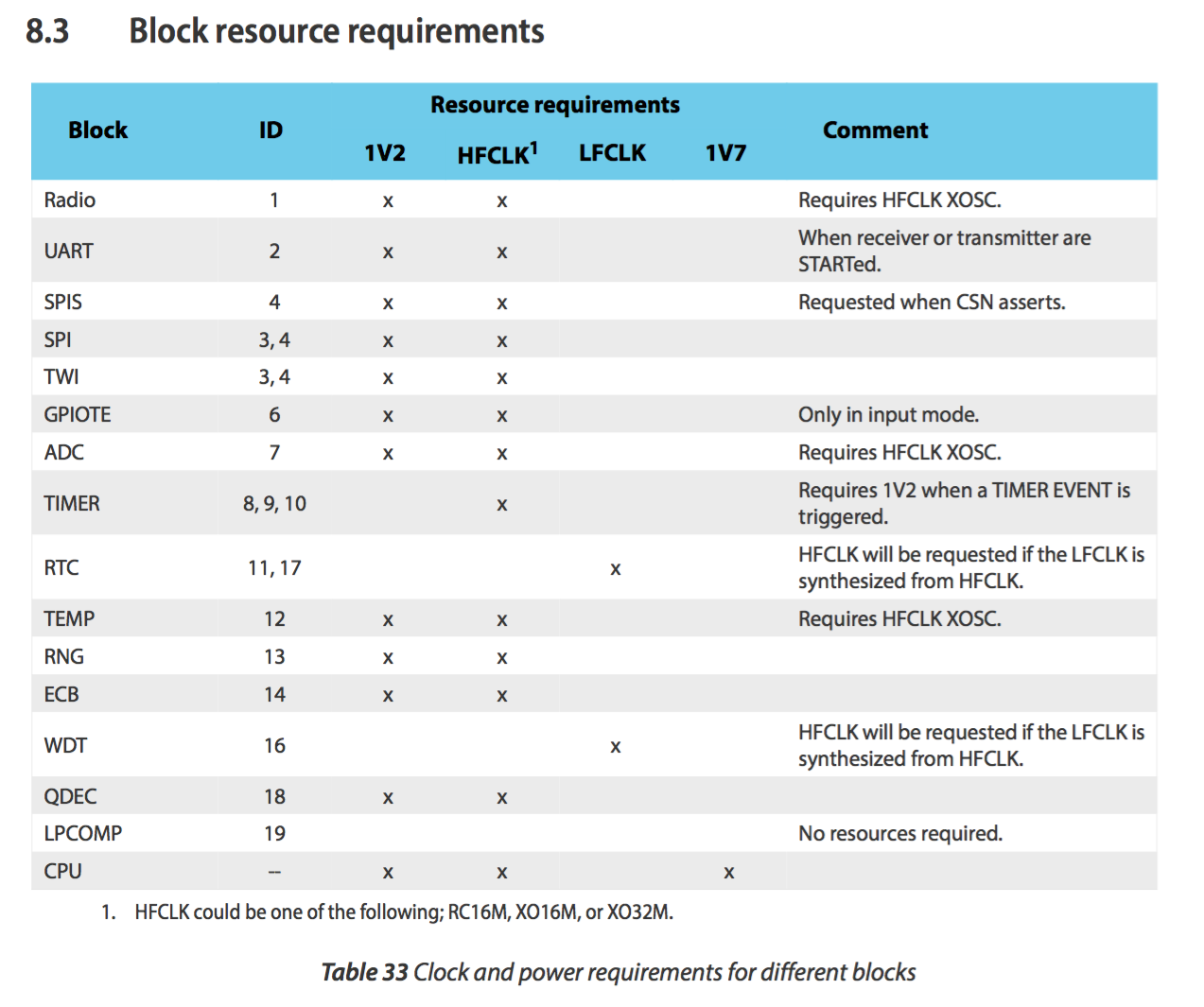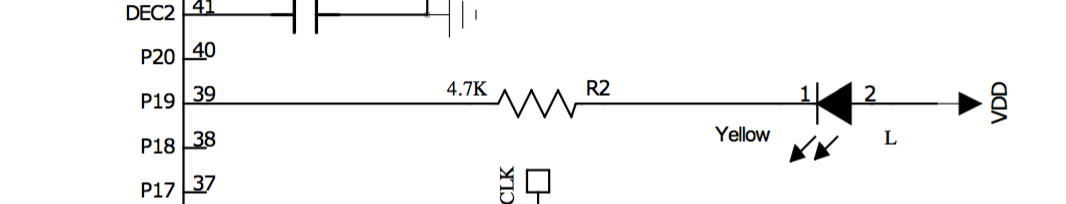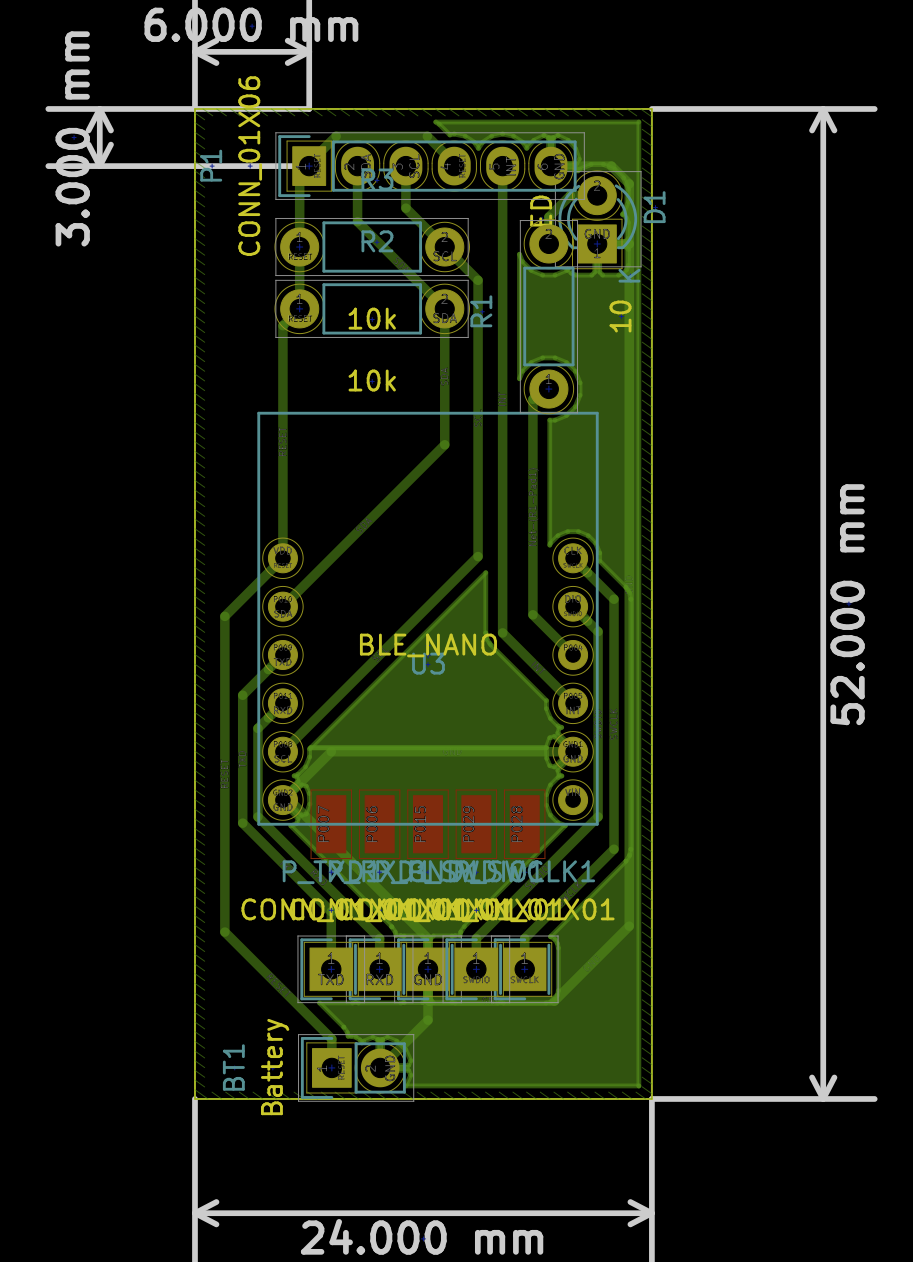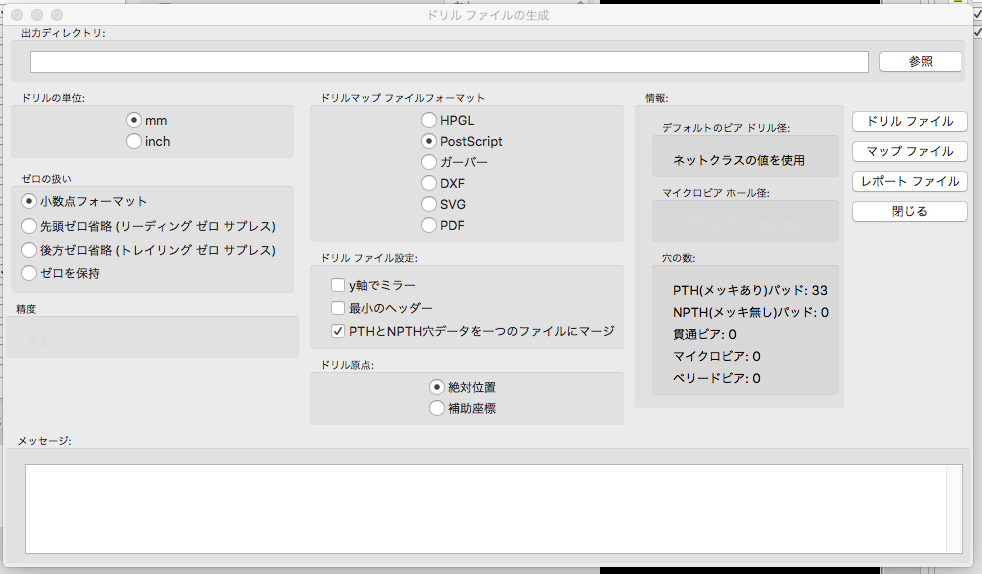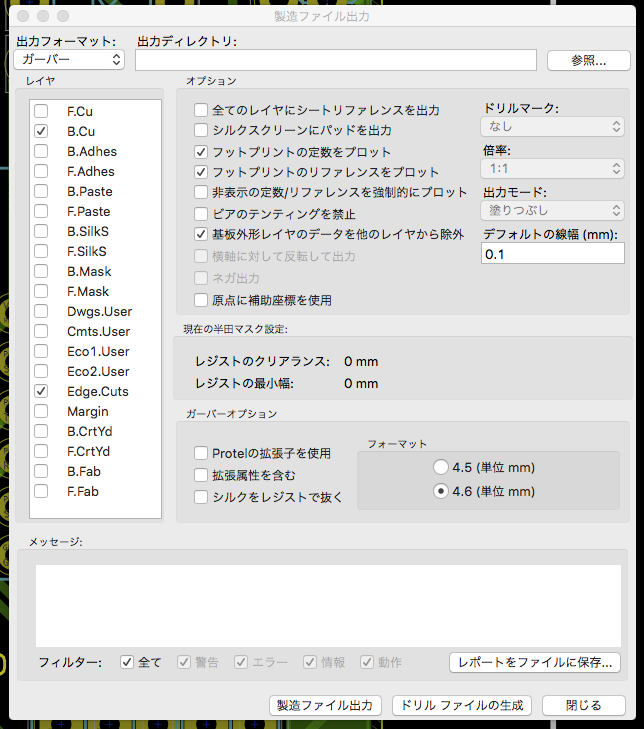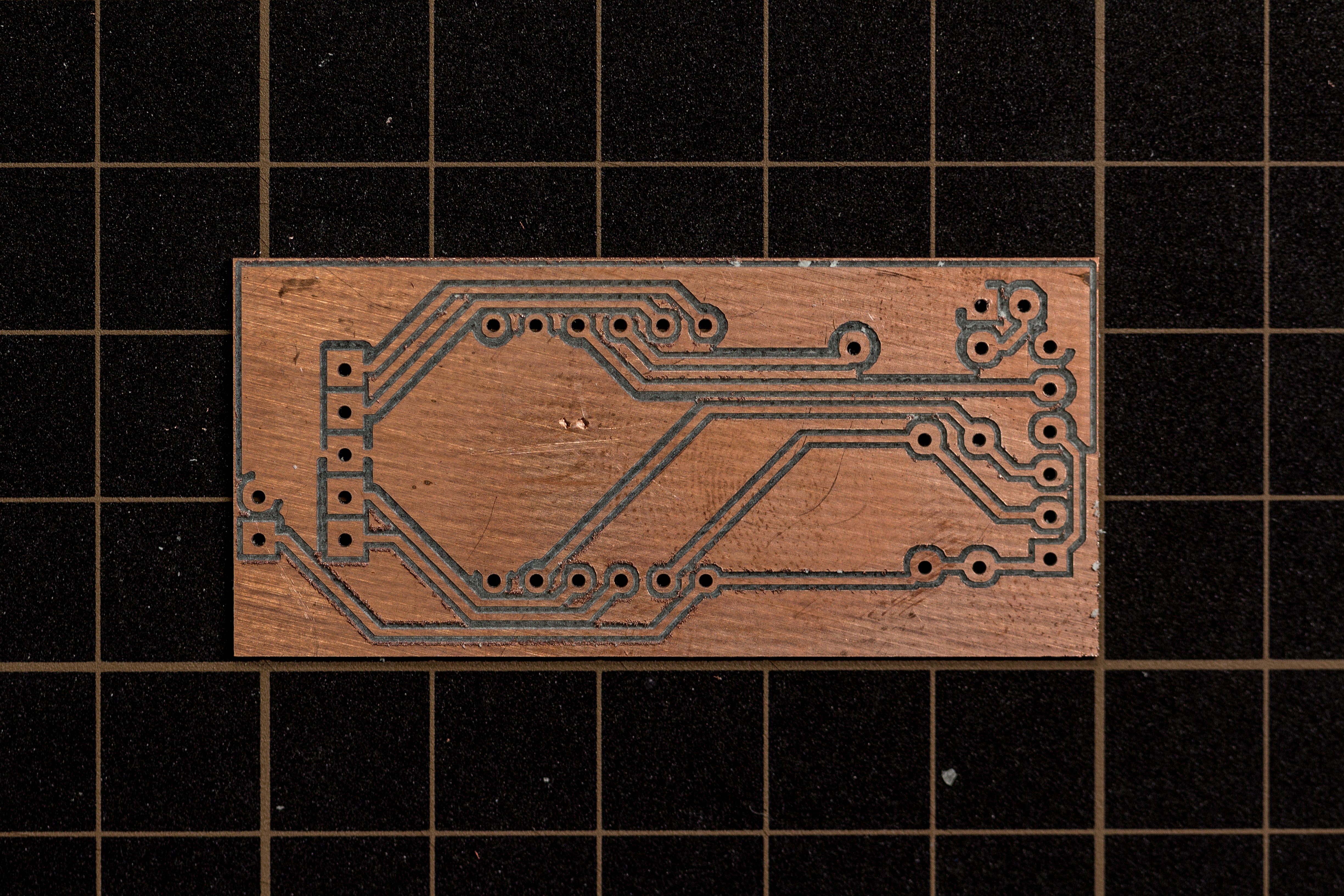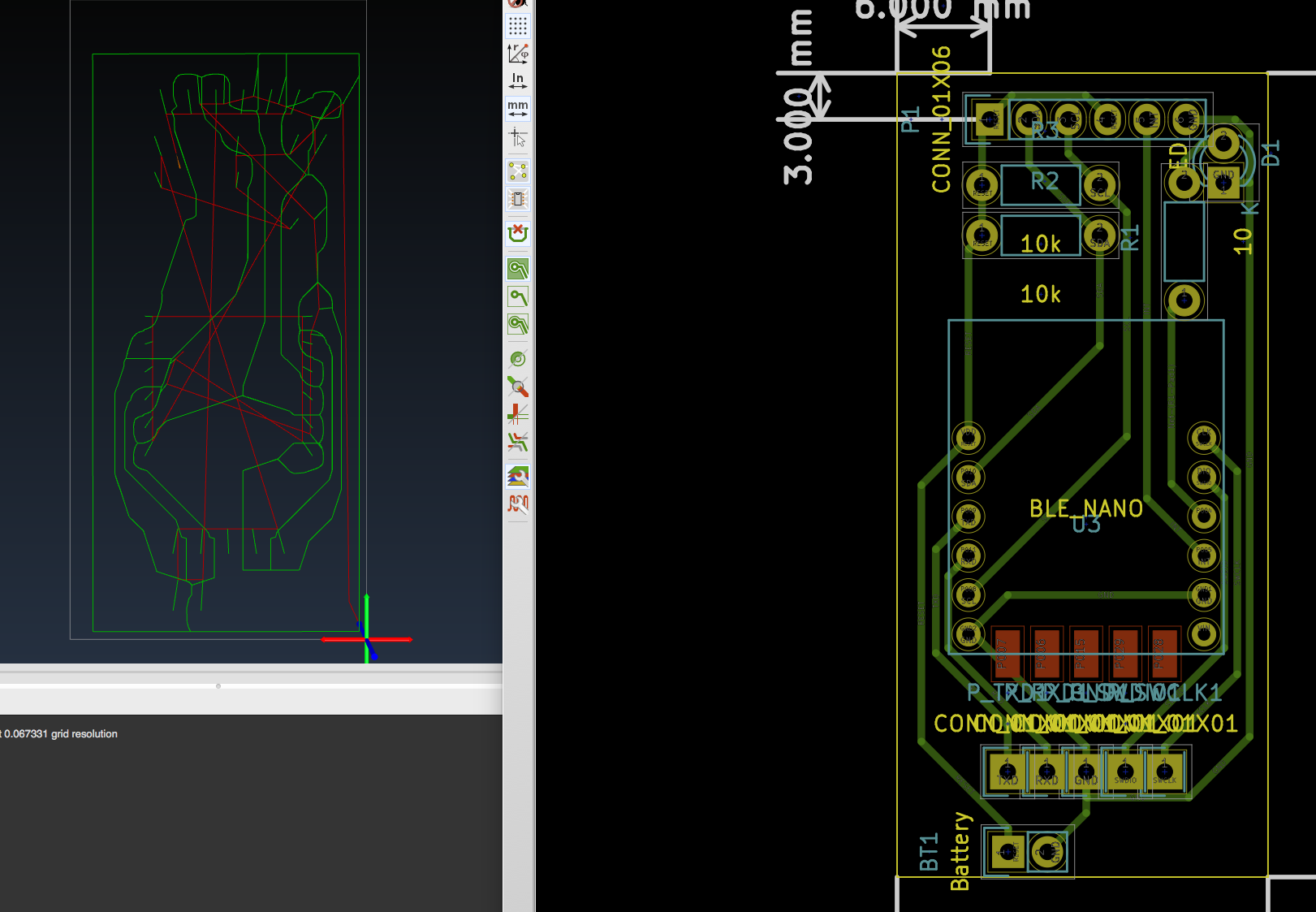スマートメータのBルートサービスで Wi-SUN モジュールを使って瞬間消費電力を読み出す | tech - 氾濫原 にひき続き Wi-SUN モジュール ROHM BP35A1 と ECHONET Lite プロトコルを使い、スマートメータから値を取得するサンプルです。
前回のコードはさすがにちゃんと動かなすぎるものなので、多少まともにしたものを書きました。一応16時間ぐらい動かしても止まることなく動く感じです。
連続して動かす場合大事なところ
- UDP 送信時の失敗処理をちゃんとやること
- タイムアウト処理をちゃんとやること
- たとえこちらからの UDP の送信に成功しても、UDPパケットがこちらに必ず受信できる保証はない
途中に環境変数で分岐していますが、片方はテスト用のコードです。Wi-SUN のスキャンが結構時間がかかってイライラするので、想定問答をシミュレーションしています。ちゃんとテスト化したほうがいいんですが、長時間実際に動かしてみるほうが有益だと思ったので限られた時間でそこまでやってません。
require 'stringio'
module ECHONET_Lite
EHD1 = 0b00010000
EHD2_DEFINED = 0x81
EHD2_ANY = 0x82
class ParseError < Exception
end
def self.parse_frame(frame)
ret = Frame.parse(frame)
unless ret.valid?
raise ParseError.new("not an ECHONET Lite frame")
end
ret
end
Frame = Struct.new(:ehd1, :ehd2, :tid, :edata) do
def self.parse(frame)
ret = self.new(*frame.unpack("CCna*"))
if ret.valid? && ret.format_defined?
ret.edata = EDATA.parse(ret.edata)
end
ret
end
def valid?
ehd1 == EHD1
end
def format_defined?
ehd2 == EHD2_DEFINED
end
def format_any?
ehd2 == EHD2_ANY
end
def pack
[ehd1, ehd2, tid].pack("CCn") + edata.pack
end
end
EDATA = Struct.new(:seoj, :deoj, :esv, :opc, :properties) do
def self.parse(edata)
ret = self.new(*edata.unpack("a3a3CCa*"))
ret.seoj = EOJ.parse(ret.seoj)
ret.deoj = EOJ.parse(ret.deoj)
props = []
StringIO.open(ret.properties) do |io|
ret.opc.times do
epc, pdc = *io.read(2).unpack("CC")
edt = io.read(pdc)
props << Property.new(epc, pdc, edt)
end
end
ret.properties = props
ret
end
def pack
seoj.pack + deoj.pack + [esv, opc].pack("CC") + properties.map {|i|
i.pack
}.join
end
end
EOJ = Struct.new(:class_group_code, :class_code, :instance_code) do
def self.parse(eoj)
self.new(*eoj.unpack("CCC"))
end
def pack
to_a.pack("CCC")
end
end
Property = Struct.new(:epc, :pdc, :edt) do
def pack
self.pdc = edt.length
[epc, pdc].pack("CC") + edt
end
end
end
require 'thread'
class SKSTACK_IP
EVENT_RECV_NS = 1
EVENT_RECV_NA = 2
EVENT_RECV_ECHO = 5
EVENT_COMPLETED_ED_SCAN = 0x1F
EVENT_RECV_BEACON = 0x20
EVENT_UDP_SENT = 0x21
EVENT_COMPLETED_ACTIVE_SCAN = 0x22
EVENT_PANA_ERROR = 0x24
EVENT_PANA_COMPLETED = 0x25
EVENT_RECV_SESSION_CLOSE = 0x26
EVENT_PANA_CLOSED = 0x27
EVENT_PANA_TIMEOUT = 0x28
EVENT_SESSION_EXPIRED = 0x29
EVENT_SEND_LIMIT = 0x32
EVENT_SEND_UNLOCK = 0x33
def initialize(port)
@event_callbacks = {}
@port = port
@port.set_encoding(Encoding::BINARY)
@rest = nil
@queue = Queue.new
@read_thread = Thread.start do
Thread.current.abort_on_exception = true
buffer = ""
while true
c = @port.getc
if c.nil?
raise "unexpected IO closed"
end
buffer << c
case c
when ' ', "\r"
command = buffer.sub(/[\r ]$/, '')
case command
when "ERXUDP"
event = {}
event[:sender] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:dest] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:rport] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '').unpack("n")[0]
event[:lport] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '').unpack("n")[0]
event[:senderlla] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:secured] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
datalen = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:data] = @port.read(datalen.to_i(16))
@port.read(2)
callback_event(:ERXUDP, event)
buffer.clear
when "ERXTCP"
event = {}
event[:sender] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:rport] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:lport] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
datalen = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:data] = @port.read(datalen.to_i(16))
@port.read(2)
callback_event(:ERXTCP, event)
buffer.clear
when "EPONG"
event = {}
event[:sender] = @port.gets("\n").sub(/\s+$/, '')
callback_event(:EPONG, event)
buffer.clear
when "ETCP"
event = {}
event[:status] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
if event[:status] == "1"
event[:handle] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:ipaddr] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:rport] = @port.gets(" ").sub(/\s+$/, '')
event[:lport] = @port.gets("\n").sub(/\s+$/, '')
else
event[:handle] = @port.gets("\n").sub(/\s+$/, '')
end
callback_event(:EPONG, event)
buffer.clear
when "EADDR", "ENEIGHBOR"
when "EPANDESC"
event = {}
@port.gets("\n")
event[:channel] = @port.gets("\n")[/Channel:(\S+)/, 1]
event[:channel_page] = @port.gets("\n")[/Channel Page:(\S+)/, 1]
event[:pan_id] = @port.gets("\n")[/Pan ID:(\S+)/, 1]
event[:addr] = @port.gets("\n")[/Addr:(\S+)/, 1]
event[:lqi] = @port.gets("\n")[/LQI:(\S+)/, 1]
event[:pair_id] = @port.gets("\n")[/PairID:(\S+)/, 1]
p event
callback_event(:EPANDESC, event)
buffer.clear
when "EEDSCAN"
@port.gets("\n")
_rssi = @port.gets("\n")
when "EPORT"
@port.gets("\n")
6.times do
_udp = @port.gets("\n")
end
@port.gets("\n")
4.times do
_tcp = @port.gets("\n")
end
@port.gets("\n")
when "EHANDLE"
@port.gets("\n")
while line = @port.gets("\n")
line.chomp!
break if line == "OK"
end
when "EVENT"
num, sender, param = *@port.gets("\n").sub(/\s+$/, '').split(/ /)
event = {
num: num,
sender: sender,
param: param
}
callback_event(:EVENT, event)
buffer.clear
when "EVER"
event = {}
event[:version] = @port.gets("\n").sub(/\s+$/, '')
callback_event(:EVER, event)
buffer.clear
when "EAPPVER"
event = {}
event[:version] = @port.gets("\n").sub(/\s+$/, '')
callback_event(:EAPPVER, event)
buffer.clear
else
end
when "\n"
line = buffer.chomp
@queue << line
buffer.clear
end
end
end
end
def command(string)
@port.write(string + "\r\n")
res = @queue.pop
if string.split(/ /)[0] == res.split(/ /)[0]
res = @queue.pop
end
res
end
def on(name, &block)
(@event_callbacks[name.to_sym] ||= []) << block
end
private
def callback_event(name, event)
(@event_callbacks[name.to_sym] || []).each do |cb|
cb.call(event)
end
end
end
require 'logger'
require 'timeout'
class SmartMeterController
def initialize
@logger = Logger.new($stdout)
end
def start(io, opts)
@stack = SKSTACK_IP.new(io)
@events = Queue.new
@stack.on(:EVENT) do |e|
@logger.debug("EVENT %p" % e)
@events << e
end
@epandesc = nil
@stack.on(:EPANDESC) do |e|
@logger.debug("EPANDESC %p" % e)
@epandesc = e
end
@transactions = {}
@stack.on(:ERXUDP) do |e|
@logger.info("ERXUDP %p" % e)
begin
frame = ECHONET_Lite.parse_frame(e[:data])
if transaction = @transactions.delete(frame.tid)
transaction.call(frame)
end
rescue ECHONET_Lite::ParseError
@logger.info("Not an ECHONET Lite frame")
end
end
@stack.on(:EVER) do |e|
@logger.info("EVER %p" % e)
end
@stack.on(:EAPPVER) do |e|
@logger.info("EAPPVER %p" % e)
end
@stack.command("SKRESET") == "OK" or raise
@stack.command("SKVER") == "OK" or raise
@stack.command("SKAPPVER") == "OK" or raise
@stack.command("SKSREG SFE 0") == "OK" or raise
@logger.info("Setting ID and Password")
@stack.command("SKSETPWD C #{opts[:PASS]}") == "OK" or raise
@stack.command("SKSETRBID #{opts[:ID]}") == "OK" or raise
while true
@logger.info("Scanning device...")
@stack.command("SKSCAN 2 FFFFFFFF 6")
while e = @events.pop
if e[:num].to_i(16) == SKSTACK_IP::EVENT_COMPLETED_ACTIVE_SCAN
@logger.info("Scan Completed")
break
end
end
if @epandesc
break
end
@logger.info("Device not found... retrying...")
sleep 1
end
@logger.info("Device found %p" % @epandesc)
@logger.info("Getting IPv6 Address from MAC Address (%p)" % @epandesc[:addr])
@ipv6_addr = @stack.command("SKLL64 #{@epandesc[:addr]}")
@logger.info("Setting Channel and Pan ID")
@stack.command("SKSREG S2 #{@epandesc[:channel]}") == "OK" or raise
@stack.command("SKSREG S3 #{@epandesc[:pan_id]}") == "OK" or raise
@logger.info("Starting PANA")
@stack.command("SKJOIN #{@ipv6_addr}") == "OK" or raise
while e = @events.pop
case e[:num].to_i(16)
when SKSTACK_IP::EVENT_PANA_COMPLETED
break
when SKSTACK_IP::EVENT_PANA_ERROR
raise "pana error"
end
end
@logger.info("PANA Completed")
@tid = 0
end
def retrieve_power
@tid += 1
tid = @tid
q = Queue.new
@transactions[tid] = proc {|frame|
q << frame
}
frame = ECHONET_Lite::Frame.new(
ECHONET_Lite::EHD1,
ECHONET_Lite::EHD2_DEFINED,
@tid,
ECHONET_Lite::EDATA.new(
ECHONET_Lite::EOJ.new(0x05, 0xFF, 0x01),
ECHONET_Lite::EOJ.new(0x02, 0x88, 0x01),
0x62,
1,
[
ECHONET_Lite::Property.new(
0xe7,
0x00,
""
)
]
)
)
handle = 1
port_num = 3610
sec = 1
data = frame.pack
p [:packed, data]
@stack.command("SKSENDTO %s %s %04X %s %04X %s" % [
handle,
@ipv6_addr,
port_num,
sec,
data.length,
data
])
while e = @events.pop
if e[:num].to_i(16) == SKSTACK_IP::EVENT_UDP_SENT
unless e[:param].to_i(16) == 0
return nil
end
break
end
end
ret = nil
begin
Timeout.timeout(5) do
ret = q.pop
end
rescue Timeout::Error
@logger.info "UDP Response Timeout"
@transactions.delete(tid)
end
ret
end
end
io = nil
if ENV["PORT"].nil?
require 'socket'
s1, s2 = Socket.pair(:UNIX, :STREAM, 0)
Thread.start do
while l = s2.gets
l.chomp!
case l
when "SKVER"
s2 << "SKVER\r\n"
s2 << "EVER 1.2.10\r\n"
s2 << "OK\r\n"
when "SKSREG SFE 0"
s2 << "SKSREG SFE 0\r\n"
s2 << "OK\r\n"
when /^SKSETPWD/
s2 << "OK\r\n"
when /^SKSETRBID/
s2 << "OK\r\n"
when "SKSCAN 2 FFFFFFFF 6"
s2 << "OK\r\n"
s2 << "EVENT 20 FE80:0000:0000:0000:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX\r\n"
s2 << "EPANDESC\r\n"
s2 << " Channel:2F\r\n"
s2 << " Channel Page:09\r\n"
s2 << " Pan ID:A0E6\r\n"
s2 << " Addr:001C64000357XXXX\r\n"
s2 << " LQI:84\r\n"
s2 << " PairID:00AXXXXX\r\n"
s2 << "EVENT 22 FE80:0000:0000:0000:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX\r\n"
when /^SKLL64/
s2 << "FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY\r\n"
when /^SKSREG S2/
s2 << "OK\r\n"
when /^SKSREG S3/
s2 << "OK\r\n"
when /^SKJOIN/
s2 << "OK\r\n"
s2 << "EVENT 21 FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY 02\r\n"
s2 << "EVENT 02 FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY\r\n"
s2 << "ERXUDP FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY FE80:0000:0000:0000:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX 02CC 02CC 001C64000357XXXX 0 0028 (����O�y\r\n"
s2 << "EVENT 21 FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY 00\r\n"
s2 << "ERXUDP FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY FE80:0000:0000:0000:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX 02CC 02CC 001C64000357XXXX 0 0068 h����O�z$�r%^a�;H)��#L�8�8/�4+�u\-����&ѨSM00000099021000000000000000AXXXXX\r\n"
s2 << "EVENT 21 FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY 00\r\n"
s2 << "ERXUDP FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY FE80:0000:0000:0000:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX 02CC 02CC 001C64000357XXXX 0 0054 T����O�{;�;/��4+�u\-����&Ѩ��?s�����r��2���0��D�R��\r\n"
s2 << "EVENT 21 FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY 00\r\n"
s2 << "ERXUDP FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY FE80:0000:0000:0000:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX 02CC 02CC 001C64000357XXXX 0 0058 X����O�|� Q�{��(F���.�[�<\r\n"
s2 << "EVENT 21 FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY 00\r\n"
s2 << "EVENT 25 FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY\r\n"
when /SKSENDTO/
s2 << "ERXUDP FE80:0000:0000:0000:YYYY:YYYY:YYYY:YYYY FE80:0000:0000:0000:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX 0E1A 0E1A 001C64000357XXXX 1 0012 \x10\x81\x00\x01\x02\x88\x01\x05\xFF\x01r\x01\xE7\x04\x00\x00\x04Z\r\n"
end
end
end
io = s1
else
require 'serialport'
begin
io = SerialPort.new(
"/dev/tty.usbserial-A500YQPG",
115200,
8,
1,
0
)
rescue Errno::EBUSY
sleep 1
retry
end
end
c = SmartMeterController.new
c.start(io, {
ID: "0000 00XX 0XXX 0000 0000 0000 XXXX XXXX".gsub(/ /, ''),
PASS: "XXXX XXXX XXXX".gsub(/ /, ''),
})
loop do
frame = c.retrieve_power
unless frame
puts "failed to get power"
next
end
frame.edata.properties.each do |prop|
p prop
if prop.epc == 0xe7 && prop.pdc == 4
watts = prop.edt.unpack("N")[0]
p "#{watts} W"
end
end
end
-
トップ
-
tech
-
スマートメータから瞬間消費電力を読むRubyのコード